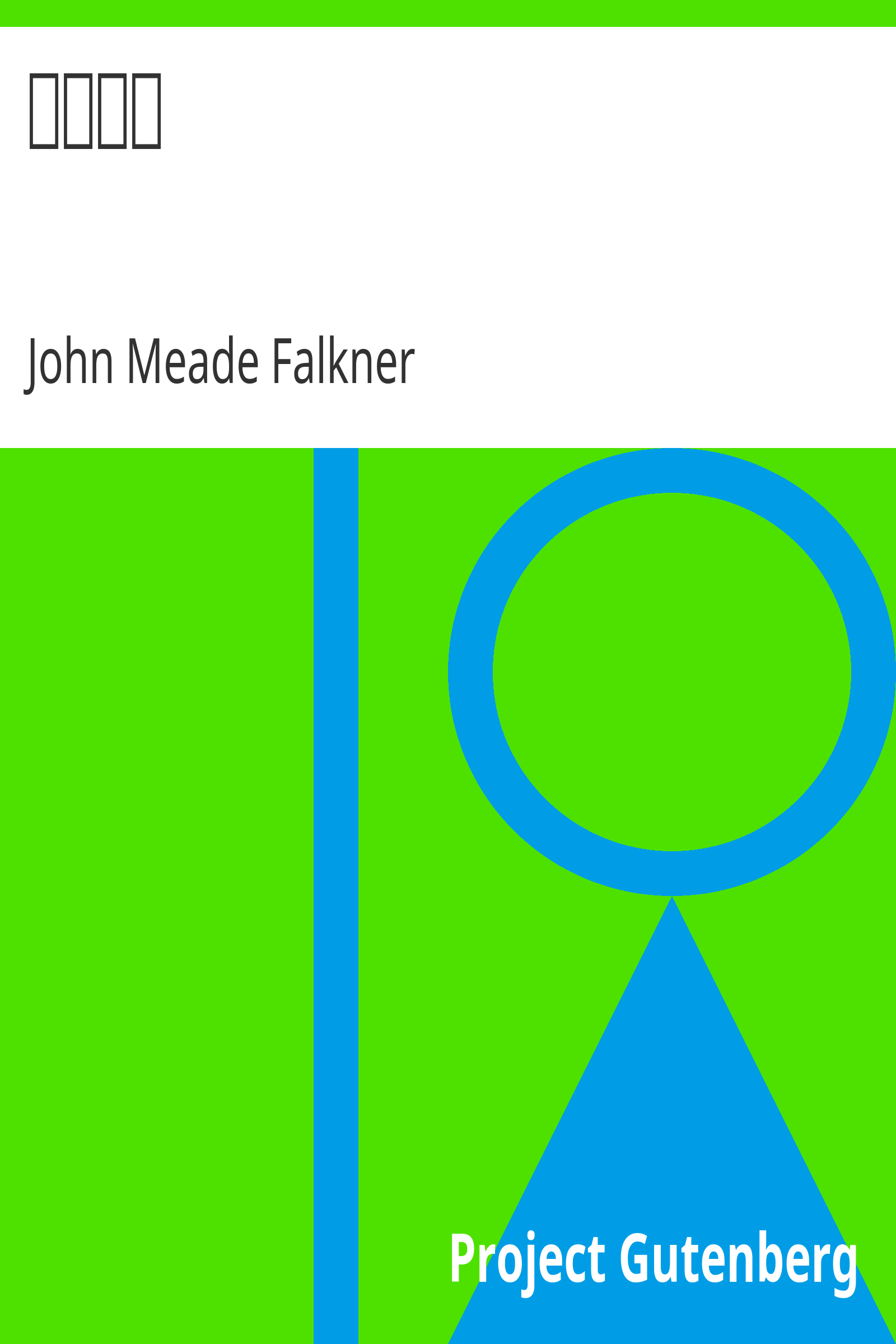雲形紋章
Play Sample
彼女の父親マーチン・ジョウリフは死ぬまでその美貌を保ち、自分でもそのことをよく知っていた。若いときは整った目鼻立ちを誇りにし、歳を取ってからは身だしなみに注意を払った。暮らしぶりがどん底に落ちこんだときでさえ、彼は仕立てのいい服を手に入れようとした。いつも最新流行の服というわけにはいかなかったが、それらは背の高い、姿勢のしゃんとした彼にはよく似合った。人は彼のことを「紳士ジョウリフ」と呼んで笑ったが、カランでしばしば聞かれる悪口と違って、そこにはそれほど嫌味がこめられていなかったようだ。むしろ農夫の息子がどこであんな物腰を身につけたのかと不思議がられた。マーチン自身にとっては貴族的な態度は気取りというより義務だった。彼の立場がそれを要求するのだ。なぜなら彼は自分のことを、権利を剥奪されたブランダマー家の人間と思いこんでいたからである。
グローヴ家のミス・ハンターが、父親のハンター大佐から、身分違いもはなはだしい、あんな男と結婚したら勘当だ、と固く言い渡されていたにもかかわらず、彼と駆け落ちしたのは、四十五才になっても彼の男っぷりがよかったからである。実は彼女は父親の不興に長く耐えることなく、最初の子供を産んだときに亡くなってしまった。この悲しい結末さえ大佐の心を和らげることはできなかった。小説に見られる前例をことごとく覆し、大佐は幼い孫娘に少しも関心を示さず、あまりの世間体の悪さにカランから引っ越してしまったのである。マーチンもまた親としての義務を真剣に受け止めるような男ではなく、子供の養育はミス・ジョウリフに任された。彼女の苦労が一つ増えたわけだが、しかしそれ以上に彼女は喜びを感じた。マーチンは娘をアナスタシアと名付けたことで充分に自分の責任を果たしたと考えていた。この名前はディブレット貴族名鑑によると、ブランダマー家の女性によって代々引き継がれてきた名前なのだそうだ。このひときわ輝かしい愛の証拠を与えたあと、彼はまた家系調査のため断続的につづく放浪の旅に出かけ、五年間カランに戻ってこなかった。
その後何年もマーチンは娘をほったらかしにし、ときどきカランに戻っては来たものの、いつも雲形紋章に対する自分の権利を確立することに熱中し、アナスタシアの教育と扶養はすっかり妹にまかせて満足していた。彼がはじめて親としての権威を振りかざしたのは、娘が十五になったときだった。その頃久しぶりに家に戻った彼は、妹のミス・ジョウリフにむかって、姪の教育がけしからぬほどなおざりにされていると指摘し、このような嘆かわしい状態はすぐさま改められなければならないと言った。ミス・ジョウリフは悲しそうに自分の至らなさを認め、自分の怠慢を許して欲しいとマーチンに嘆願した。彼女は、下宿の管理や、自分とアナスタシアの生計を立てる必要が、教育に宛てるべき時間を甚だしく減らしているとか、手元不如意のために教師を雇って自分のあまりにも限られた教育を補うことができないのだ、などと言い訳しようとは夢にも思わなかった。実際、彼女がアナスタシアに教えられることといったら、読み書き、算数、地理を少々、「マグノール先生の質問集」から得た微々たる知識、見事な針使い、詩と小説に対するつきることのない愛、カランでは奇特というべき隣人への思いやり、そしてブランダマー家最上のしきたりとは残念ながら相容れぬ神への畏れ、せいぜいがこの程度であったのである。
ブランダマー家にふさわしい育て方をしていない、とマーチンは言った。令嬢アナスタシアとなったときに、どうしてその任に耐えることができるというのか。フランス語を勉強させなければならない。ミス・ジョウリフが教えたような初歩ではなくて。彼は妹の真似をして「ドゥ、デラ、デラポトロフ、デイ」と言って笑い、彼女のしなびた頬を真赤にさせ、テーブルの下で叔母の手を握っていたアナスタシアを泣かせた。そんなフランス語じゃなくて、上流階級で通用するようなちゃんとしたやつだ。それから音楽、これは必須科目だ。ミス・ジョウリフは、家事と痛風が共謀して節くれ立った指からしなやかさを奪うまで、自分が低音部を受け持ってアナスタシアとやさしいピアノの二重奏をしたことを恥ずかしさとともに思い出し、また顔を赤らめた。姪と二重奏するのは大きな喜びだったが、しかしもちろんおよそ下手くそなものでしかなかったろうし、自分が子供のときに弾いた曲だからおそろしく流行遅れだったに違いない。しかもピアノもウィドコウムの客間にあった、あの同じピアノだった。
そういうわけで彼女はマーチンが改善計画を提示するあいだ熱心に耳を傾けた。この計画とはアナスタシアを州都カリスベリにあるミセス・ハワードの寄宿学校に送ることに他ならなかった。この目論見を聞いて妹は息をのんだ。ミセス・ハワードの学校といえば、名門の教養学校であり、カランのご婦人方の中で娘をそこに送っているのはミセス・ブルティールだけだったのだ。しかしマーチンの高潔な寛容は留まるところを知らなかった。「そうと決まれば善は急げだ。やるべきことはさっさとやってしまおう」彼はポケットから粗布の袋を取り出し、テーブルの上にソヴリン金貨の小山を築いて議論に決着をつけた。兄がどうやってそんな富を得たのかというミス・ジョウリフの驚きは、彼の度量の大きさに対する感嘆の念によってかき消された。この富のほんの一部でベルヴュー・ロッジの逼迫した財政状態が緩和されるのに、と束の間彼女が思ったとしても、彼女はそんなぼやきを圧し殺し、天が与えたアナスタシアの教育費用に熱烈な感謝を捧げた。マーチンはテーブルのソヴリン金貨を数えた。前払いしてアナスタシアの印象をよくしたほうがいいと言われて、ミス・ジョウリフは賛成し、大いに胸をなで下ろした。彼女は学期終了前にマーチンがまた旅に出て、支払いを彼女に押しつけるのではないかとびくびくしていたのだ。
こうしてアナスタシアはカリスベリに行った。ミス・ジョウリフはみずからに課した規則を破って、幾つもの小さな借金を背負いこんだ。というのは当時持っていたような貧相な支度で姪を学校にやりたくはなかったし、かといってよりよい支度を買うには、手持ちの金がなかったのだ。アナスタシアはカリスベリで半期を二回過ごした。音楽の腕前は大いに上がり、退屈で気のない練習をさんざん積んだあげく、タールベルクの「埴生の宿」による変奏曲をつっかえながら弾くことができるようになった。しかしフランス語は本格的なパリのアクセントを習得できず、ときには習いはじめの頃の「ドゥ、デラ、デラポトロフ、デイ」に逆戻りすることもあった。もっともそうした欠点が後に深刻な不都合を招いたことはなかったようだけれど。教養を身につける以外にも、彼女は中流上層に属する三十人の子女と交わる特権を楽しみ、善悪を知る木から、それまでは気づきもしなかった果実を食べた。しかし第二学期の終わりに彼女はこれらの恵まれた機会を放棄せざるを得なかった。マーチンが娘の授業料を永続的に準備することなくカランを離れ、ミセス・ハワードの学校案内には重力の法則のごとき厳然たる規則があったのだ。すなわち、前学期の学費を納めていない場合は、いかなる生徒も学校に戻ることを許可せずという規則が。
アナスタシアの学校生活はこれをもって終了した。カリスベリの空気は彼女の健康によくないなどといった説明がなされたが、彼女がその本当の理由を知ったのは、それからほぼ二年後のことで、そのころにはミス・ジョウリフの勤勉と禁欲が、ミセス・ハワードへのマーチンの負債をほぼ払い終えていた。娘のほうはカランにいられることが嬉しかった。彼女はミス・ジョウリフを深く慕っていたからだ。しかし経験という点では彼女はずっと大人びて戻ってきた。視野は広がり、人生をいっそう深く見通すことができるようになりはじめていた。こうした広がりを持った考え方は好ましい実も結んだが、好ましくない実も結んだ。父親の性格をより公正に評価するようになったからである。父親がまた戻ってきたとき、彼女はそのわがままや、妹の愛情につけこむやり方に我慢がならなかった。
このような事態はミス・ジョウリフを大いに悲しませた。彼女は姪を愛し、崇拝にも似た気持ちすら持っていたのだが、同時に彼女は非常に良心的で、子供は何よりもまず親を敬うべきだということを忘れなかった。そういうわけで彼女は、アナスタシアがマーチンより自分に愛着を覚えていることを悲しまなければならないと考えたのだ。姪が誰よりも自分を愛しているということに、しかるべき不満を抱けないことがあったとしても、そんな自分の心の弱さを償うために彼女は姪といっしょにいる機会を犠牲にし、チャンスがあれば彼女を父親と二人きりで過ごさせようと努力した。真の基盤がないところに愛情を生じさせようとする努力が永遠に不毛であるように、それは無駄な努力に終わった。マーチンは娘と一緒にいることにうんざりした。彼は一人でいることを好み、彼女を料理と掃除と繕いをする機械としかみなしていなかったのだ。アナスタシアはそんな態度に憤慨し、おまけに父親の聖書たるぼろぼろに破れた貴族名鑑とか、口を開けばいつも飛び出す家系調査だの、雲形紋章にまつわる専門用語だのには何の関心も持てなかった。その後、彼が最後の帰還を遂げたとき、彼女は義務感から模範的な辛抱強さで身の回りの世話や看護をし、親への敬愛がすることをうながす、ありとあらゆる親孝行をやってのけた。父の死は安堵ではなく悲しみをもたらしたのだと信じこもうとし、それがうまくいって叔母はその点についてはなんらの疑いも持たなかった。
マーチン・ジョウリフの病気と死はアナスタシアを医者や聖職者と接触させ、それによって彼女は人生経験をさらに深めた。ブランダマー卿の名乗りを聞いても、その衝撃に耐え、ほんの少し顔を赤らめるだけで目に見えるような当惑のしるしを一つも見せなかったのは、疑いもなくこうした修練とミセス・ハワードの学校が与えた上流階級との付き合いのおかげだった。
「あら、もちろんミスタ・ウエストレイの部屋でお書きになって結構ですわ。ご案内しましょう」
彼女は部屋へ案内し、書くための道具を用意すると、ミスタ・ウエストレイの椅子に心地よく腰かける卿を残して部屋を出た。出しなに後ろ手でドアを閉めようとしたとき、何かが彼女を振り返らせた――もしかしたらそれは単なる若い女の気まぐれだったのかも知れないし、あるいは見つめられているという意識がときどき人間に及ぼす曰く言い難い魔力のせいだったのかも知れない。とにかく後ろを見たとき、彼女はブランダマー卿と目がかち合い、彼女は自分の愚かしさに腹を立てドアをぴしゃりと閉めた。
彼女は台所に戻った。神の手の台所はあまりにも広かったので、ミス・ジョウリフとアナスタシアはその一部を居間の代わりに使っていた。彼女は「ノーサンガー・アベイ」から鉛筆を抜き取り、自分の身をその舞台であるバースに送りこもうとした。五分前は彼女も鉱泉室にいて、ミセス・アレンやイザベラ・ソープやエドワード・モーランドがどこに座っているか、そしてキャサリンがどこに立っていて、ティルニーが歩み寄ってきたときジョン・ソープが彼女に何を話していたのか、正確に知っていたのである。ところがどうだろう!アナスタシアは二度とそこに入ることができなかった。灯りは消え、鉱泉室は真暗だった。五分間のあいだに悲しむべき変化が起きたのだ。入会の難しいこの団体は、もはやミス・アナスタシア・ジョウリフの興味の中心ではないことを知り、憤然として解散してしまったのである。彼らがいなくなっても、もちろん彼女は少しも寂しくなかった。彼女は自分に素晴らしい恋愛小説の才能があることを見いだしていたし、すでに胸をときめかす物語の第一章を書きはじめていたからである。
それからほぼ半時間後に叔母が帰ってきたのだが、そのあいだにミス・オースチンの騎士たちや貴婦人たちはいっそう背景に引っこみ、ミス・アナスタシアの主人公が完全に舞台を独占していた。年上のほうのミス・ジョウリフがドルカス会から戻ってきたのは、五時二十分だった。「かっきり五時二十分過ぎでしたわ」その後彼女は幾度となくそう言った。画期的な事件があると凡人はそれが起きた正確な時間に不自然なくらい重要性を付加するものである。
「お湯は沸いているかしら」台所のテーブルに座りながら彼女は尋ねた。「よかったら今日は、殿方たちが戻る前にお茶を一杯いただきたいわ。お天気はすごくむっとしているし、教室は窓が一つしか開いてなかったからとっても暑苦しくって。お気の毒にミセス・ブルティールは風が吹きこむとすぐ風邪をひくのよ。彼女の朗読の最中に眠りそうになったわ」
「すぐ用意する」とアナスタシアは言い、巧みに無関心を装ってこう付け加えた。「紳士の方が上でミスタ・ウエストレイを待っているわよ」
「あなた」ミス・ジョウリフが咎めるように叫んだ。「私がいないときにどうして人を家に入れたの。怪しげな人が大勢うろついていてすごく危ないのよ。ミスタ・ウエストレイの記念インクスタンドや、大金で買い取りの申しこみのあった花の絵があるじゃない。貴重な絵はよく額から切り取られてしまうの。泥棒なんて何をしでかすか分かりゃしないんだから」
アナスタシアの唇には微かな笑みが浮かんでいた。
「心配しなくても大丈夫よ、フェミー叔母さん。紳士の方だってことは間違いないんですもの。これがその人の名刺よ。ほら!」彼女はただならぬ秘密を帯びた一片の白い厚紙をミス・ジョウリフに手渡し、叔母が眼鏡をかけてそれを読む様子を見ていた。
ミス・ジョウリフは名刺に焦点を合わせた。「ブランダマー卿」と、たった二つのことばが実に平々凡々とした字で書かれているだけだったが、それは魔法のような効果をあらわした。疑心暗鬼はたちどころに消え、輝くばかりの驚きが顔に広がった。そのさまは、ローマ帝国軍旗の幻を見たコンスタンティン大帝もかくやと思われた。彼女は徹頭徹尾浮き世離れした女で、現世の何ものにも価値を置かず、ひたすら来世の到来を待ち望み、彼女よりも大きな世俗的財産を持つ者にはめったに持つことを許されない堅固な志操と悟りを胸に抱いていた。彼女の善と悪に対する観念ははっきりと定められて揺るぎなく、それにそむくくらいなら喜んで火あぶりの刑に処せられただろうし、もしかしたら無意識のうちに、文明が信仰厚き者から火刑を奪ったことを嘆いていたかも知れない。とはいえ、こうした性癖にはある種のちょっとした欠点、とりわけ有名人の名前に弱いという欠点が結びついていて、この世の高貴な人々をやや過大に評価する傾向があったのである。もしも慈善市や伝道集会の際、対等の人間として彼らとともに同じ四つの壁にはさまれたなら、彼女はその素晴らしい機会に狂喜しただろう。しかしブランダマー卿が自分の家の屋根の下にいるというのはあまりにも驚くべき、予想外の恩寵で、彼女はほとんど気が動顛してしまった。
「ブランダマー卿が!」彼女はやや落ち着きを取り戻したとき、口ごもるように言った。「ミスタ・ウエストレイの部屋が片付いていればいいんだけど。今朝、隅から隅まで掃除したんだけどね。いらっしゃるなら、あらかじめ連絡して欲しかったわ。汚れているのを見られるなんて嫌ですもの。今何をしていらっしゃるの、アナスタシア。ミスタ・ウエストレイが帰るまで待つとおっしゃったの」
「ミスタ・ウエストレイにメモを書くそうよ。書くものを探してあげたわ」
「ミスタ・ウエストレイの記念インクスタンドをお出ししたでしょうね」
「いいえ、考えもしなかった。小さい黒いインクスタンドがあって、中にたっぷりインクが入っていたから」
「なんてことでしょう、なんてことでしょう!」ミス・ジョウリフはこのとてつもない事態に思いをめぐらしながら言った。「誰も見たことのないブランダマー卿が、とうとうカランにやってきて、今この家にいるなんて。このボンネットだけ、とっておきのと取り替えてくるわ」彼女は鏡を見ながらそう言い足した。「それから御前様に歓迎の挨拶をして、なにか入り用の品がないかお尋ねするわ。ボンネットを見たら、わたしがたった今外出から戻ったところだってすぐ分かるでしょう。さもなきゃ、さっさと挨拶に来ないなんて恐ろしく怠慢な女だと思われてしまう。そうよ、ボンネットをかぶっていったほうが絶対いいわ」
アナスタシアは叔母がブランダマー卿に面会すると思うといささかとまどいを覚えた。彼女はミス・ジョウリフの度を超した熱狂や、浴びせかけずにはいられないであろうお世辞、そして地位ある人への当然の敬意でしかないのに卑屈な追従と取られかねない賞賛のことばを思った。どういうわけかアナスタシアは自分の家族が賓客の目にできるだけ好ましく映ることを願い、一瞬、ミス・ジョウリフに、呼ばれるまではブランダマー卿に合う必要などまったくないと説得しようかと思った。しかし彼女には達観したところがあって、すぐに自分で自分の愚かしさを咎めた。ブランダマー卿がどう思おうとわたしには何の関係もないわ。お帰りになるとき、ドアを開けでもしないかぎり、再び会うことなんかありはしない。ありふれた下宿屋やその住人のことなど、彼は一顧だにしないだろうし、もしそんな詰まらぬことを考えることがあったとしても、あんなに賢い人なのだから、自分とは立場が違うことを斟酌して、叔母のことを、わざとらしさはいろいろあっても善良な女だと見抜いてくれるだろう。
そこで彼女は抗議をせずに雄々しく静かに椅子に座り、ブランダマー卿とその訪問が引き起こしたくだらない興奮などきれいさっぱり忘れ去ろうと決意して「ノーサンガー・アベイ」をもう一度開いた。
第八章
ミス・ジョウリフはブランダマー卿とのおしゃべりに夢中になっているに違いない。台所で待ちながらアナスタシアは、叔母がもう降りてこないのではないかと思った。彼女は強い決意で「ノーサンガー・アベイ」に集中しようとしたが、目が活字の列を追ってもさっぱり頭に入らず、挙げ句の果てにふと気がつくと、ぱらぱらと騒々しくしきりにページをめくるばかりで、かえって空想の邪魔をしている自分に気がついたのだった。彼女はぱしんと本を閉じ、椅子から立ち上がって叔母が戻るまで台所を行ったり来たりした。
ミス・ジョウリフは訪問者の愛想のよさについて滔々とまくしたてた。
「本当に立派な人は例外なしにそういうものなのよ」彼女はほとばしるようにしゃべった。「いつも思うんだけど、貴族の方って腰が低いものよ。すっかりまわりに溶けこんで」ミス・ジョウリフはたった一度の行為を習慣とみなしてしまう、よくある誇張に陥っていた。いままで貴族と面とむかって話したことなどなかったのに、ブランダマー卿の第一印象を、まるで彼のような地位や立場の人を見てきた長い経験に基づく慎重な判断のように提示した。
「どうぞ記念インクスタンドをお使いくださいって、みすぼらしい黒いやつはのけてしまったの。すぐ分ったわ、銀のほうが使い慣れていらっしゃるものにずっと近いことは。わたしたちのこと、多少はお聞き及びのようよ。中に入れてくれた若い女性はわたしの姪かってお尋ねにまでなったんだもの。あなたよ。あなたのことよ、アナスタシア。あなたかってお訊きになったのよ。きっとどこかでマーチンにお会いになったんだと思うわ。でも、わたし、あんまり予想外のご訪問なので、本当に取り乱してしまって、お話がほとんど理解できなかった。でも、わたしが落ち着けるように絶えず気を遣ってくださって、だから、わたし、とうとう軽い飲み物でもいかがですかって思い切って訊いてみたの。『御前様、お茶を一杯さし上げたいのですが、いかがでしょうか。たいしたおもてなしはできませんが、お受けいただければとっても光栄ですわ』って。そうしたら、あなた、なんてお答えになったと思う?『ミス・ジョウリフ』――あの方はすごく魅力的な表情をなさるの――『そうしていただければ、こんなにありがたいことはありません。聖堂を歩き回ってとても疲れていましてね。それにもうちょっと時間をつぶさないとならないんです。夜の汽車でロンドンに行くので』お若いのに大変ね!(八十才を越えた先代しか知らないカランでは、ブランダマー卿はまだ若いのである)きっと何か公のお仕事でロンドンに呼ばれているのよ――上院とか宮廷とか、そんな関係だわ。他人に気を遣っていらっしゃるようだけど、同じくらいご自分にも気を遣っていただきたいわ。すごく疲れていらっしゃるみたいだし、顔つきも寂しそうなんですもの、アナスタシア。それでいてとっても思いやりがあるの。『是非お茶を一杯いただきたいです』――一語一句この通りにおっしゃったのよ――『でもそれを持ってくるのにまた階段を登ることはありませんよ。わたしが下に降りて、一緒にいただくとしましょう』ですって。
『申し訳ございません、御前様』とわたしは答えたの。『それはご容赦ください。この家はみすぼらしすぎますし、お給仕をさせていただくのは名誉なことですわ。午後の会合から戻ったばかりですので、わたしの外出着は大目に見ていただければ嬉しいんですが。姪がよくわたしを手伝うと言ってくれますけど、でも今だって彼女の若い足より、私の老いぼれた足のほうが元気だって言ってやるんです』」
アナスタシアの頬が赤くなったが何も言わなかった。叔母は話しつづけた。「そういうわけだから、さっそくお茶を持って行くわ。あなたがお茶を淹れてもいいわよ。でもお茶の葉はいつもよりたっぷりね。上流階級はそういうことでけちけちしないし、あの方もきっと濃いお茶を飲みつけていると思うわ。ミスタ・シャーノールのティーポットがいちばんいいんじゃないかしら。わたし、銀の角砂糖ばさみとJの字が入ったスプーンを一本取ってくる」
ミス・ジョウリフがお茶を持って行こうとしたとき、玄関でウエストレイに出くわした。聖堂から戻ってきたばかりの彼は、女主人の挨拶に少なからず胸騒ぎを覚えた。彼女は盆を置くと不吉な仕草と「まあ、ミスタ・ウエストレイ、何があったと思います」ということばで彼をミスタ・シャーノールの部屋に招き入れたのである。彼が最初に思ったのは、何か深刻な事故が起きたのではないか、オルガン奏者が死んだとか、アナスタシア・ジョウリフが足首をくじいたのではないかということだった。何が起きたのか、本当のことを知ったときはほっとした。彼はミス・ジョウリフが訪問者にお茶を運ぶのを数分待って、それから自分も階段を上がった。
ブランダマー卿が立ち上がった。
「勝手にお部屋にあがりこんだりして申し訳ありません。わたしのことは、もう下宿のご主人からお聞きになったでしょうね。勝手させていただいた事情についても。言うまでもありませんが、わたしはカランに関係することすべてに興味を持っています。この町のことも早速詳しく知ろうと思っています――それからここの住人のことも」彼はちょっと考えてからそう言い添えた。「まったくお恥ずかしいのですが、今は何も知らないのですよ。しかしこれは長いあいだ外国にいたせいなのです。ほんの数ヶ月前に戻ってきたばかりですから。しかしそんなことはわざわざ申し上げる必要はないでしょう。実はここに来たのは、大聖堂で行われることになっている修復計画についていくつか教えていただきたかったからなのです。そんな計画があるとは、先週まで知りませんでした」
彼の口調は落ち着いていて、澄んだ低い声がそのことばに重みと誠実さを与えていた。きれいに髭を剃ったオリーブ色の顔、整った目鼻立ちと黒い眉を見て、ウエストレイはしゃべりながらスペイン人のようだと思った。その印象は相手の慎み深く、謹厳な態度によって強められた。
「わたしに分かることなら何でも喜んでお話しますよ」と建築家は言い、棚から見取り図や書類を下ろした。
「残念ですが、今晩は時間がありません」とブランダマー卿は言った。「もうすぐロンドン行きの汽車に乗らなければならないのです。しかしよろしければ早い機会にもう一度ここに来ようと思います。たぶん、そのとき一緒に聖堂に行けると思います。あの建物にはとても愛着を感じているんです。建物自体の壮麗さもさることながら、昔の思い出もありましてね。子供の頃、まあ、ときにはとてもみじめな子供時代だったのですが、よくフォーディングからここまで遊びにきて大聖堂のあちこちをぶらぶらしながら何時間も過ごしたものです。螺旋階段や、暗い壁廊や、いわくありげな障壁や信者席を見ているとロマンチックな夢にひたってしまい、今でもその夢から完全に覚めてはいないんじゃないかという気がします。あの建物は大幅な修理の必要があると聞きました。素人目には変わったところは何もないように見えますけど。昔からずっと荒れた感じがしていたせいでしょうか」
ウエストレイは最終的にやらなければならないこと、そして今取り組もうとしていることを、手短に説明した。
「こんな具合に工事の計画は立ててあります」と彼は言った。「袖廊の天井がいちばん緊急を要することは間違いないんですが、ほかにも長く放置しておくわけにはいかないところが多々あるのです。塔の安定度にも大いに疑問があります。もっともわたしの上司はそれほど深刻には考えていないようですが。それでいいのかもしれませんけどね。というのはわれわれは資金難でにっちもさっちもいかない状態だからです。来週慈善市を開いて資金を募ろうとしているんですが、慈善市を百回催しても必要な金の半分も集まらないでしょう」
「その手の問題があることは聞いています」訪問者は考えこむように言った。「今日礼拝が終わって聖堂を出るときにオルガン奏者に会いました。わたしの正体を知らずに、何もかもブランダマー卿の責任であると、とても厳しい意見を述べていましたよ。特にオルガンを直すべきだとね。南袖廊(註 原文では「北袖廊」になっている)に関しては、わたしたちにある種の道義的責任があると思います。あそこを墓所として付属させましたから。確かブランダマー側廊と呼ばれていたと思います」
「ええ、今でもそう呼ばれていますよ」とウエストレイは答えた。会話がこういう方向に進んだことを彼は喜び、機械仕掛けの神があらわれたと思った。ブランダマー卿の次の質問はさらに彼を勇気づけた。
「袖廊の修復にはいくらかかるとお考えですか」
ウエストレイは書類をかき回して、表紙にカラン大聖堂の絵が載っている、印刷された小冊子を探しだした。
「これはサー・ジョージ・ファークワーの見積もりです」と彼は言った。「寄付を呼びかけるために各方面に送ったパンフレットなんですが、印刷費をまかなうことさえできませんでした。今どきこうしたことに金を出そうなんて人は一人もいません。ああ、これですね――南袖廊に七千八百ポンド(註 原文では「北袖廊」)」
短い沈黙がつづき、ウエストレイはまごついた。総額がブランダマー卿の予想を越えていたのだろう。いきなり金額を示したせいで、せっかくの寄付者の意気込みに水をかけてしまったのではないかと心配で顔が上がらなかった。
ブランダマー卿は話題を変えた。
「オルガンを弾いていたのは誰なんですか。あの人の態度は結構気に入ってしまいました。相当きついことをいわれましたよ。悪気はないんでしょうけど。有能な音楽家のようですね。でも楽器は無惨な有様だとか」
「確かにとても有能なオルガン奏者です」とウエストレイは答えた。ブランダマー卿が寄付する気でいるのは明らかだった。袖廊の修復費用を出すところまで気前がよくないにしろ、少なくともオルガンには幾ばくかの金を出すのではないだろうか。建築家は友人ミスタ・シャーノールのために力をつくそうとした。「彼はとても有能なオルガン奏者です」と彼は繰り返した。「シャーノールといって、この下宿に住んでいるんです。呼んできましょうか。オルガンのことをお訊きになりますか」
「いやいや、今は止めておきます。時間がありません。別の日に話し合いますよ。きっとお金はそんなにかからないでしょうね、オルガンの修理には――他の費用と比べればたいしたことはないでしょう。わたしの祖父、亡くなったブランダマー卿に、この修復費用の話を持ちかけなかったのですか」
寄付に対するウエストレイの期待は再び打ち砕かれ、こんなふうに話をそらすのは彼にはいささか蔑むべきことのように思われた。ブランダマー卿が不必要なまでに愛情をこめて聖堂を賛美したすぐあとだっただけに見苦しい感じがした。
「ええ、参事会員のパーキン、ここの主任司祭が先代のブランダマー卿に手紙を書いて、聖堂修復費用の寄付をお願いしたんですが、梨のつぶてでした」
ウエストレイはその口調に皮肉めいたものを含ませたのだが、しゃべり終わるよりも先に自分の無礼なことば遣いを後悔していた。しかし人によっては怒るようなことを言ったのに、相手は少しも気にしていないようだった。
「ああ、わたしの祖父は実に嘆かわしい老人でした。さあ、もう行かないと、汽車に遅れてしまいます。この次カランに来たときはミスタ・シャーノールに紹介してください。聖堂を見せてくださるって約束でしたよね。よろしいですか」
「ええ――ああ、もちろんですよ」とウエストレイは言ったが、さっきほど誠意のこもった話し方ではなかった。彼はブランダマー卿が寄付の約束をしなかったことに失望し、彼に付き添って階段下まで降りるときは、半時間ほど品物を物色したあと、考えてまた来るなどと言って帰ってしまうご婦人をもてなした、店員のような気分だった。
ミス・ジョウリフは台所の階段に立って待っていたおかげで、玄関ホールでまったく偶然にもブランダマー卿と会うことができた。彼女は新たな敬意の表明とともに正面玄関のドアを開けて彼を外に導いた。彼女は彼がけちくさく寄付を回避したことを知らなかったし、彼女にとって御前様は何があろうと御前様なのである。彼は立ち去るとき彼女と握手して、今度カランに来たときもお茶をご馳走してくださいねと言い、彼がふりまくあらゆる魅力と親切に最後の仕上げを施した。
ブランダマー卿がベルヴュー・ロッジの外の階段を降りていくとき、日はかげりはじめていた。いつもより早く日が暮れたのだろう、訪問者が上の階にあがってすぐ、アナスタシアは台所が暗すぎて本が読めないことに気がついた。そこで彼女は本を持ってミスタ・シャーノールの部屋へ行き、窓辺の席に座った。
そこはミスタ・シャーノールが外出しているときも、家にいるときも、彼女が好んでよく行く場所だった。ミスタ・シャーノールは子供のときから彼女を知っていたし、作曲しているとき静かに読書する優雅な娘の姿を見るのが好きだったのだ。奥行きのある窓辺の腰掛けはペンキを塗った樅の板で作られていた。背に沿って色あせたクッションが垂れ下がっていて、窓が開いているときは上に持ちあげ窓枠に載せることができ、夏の夜など、誰でも肘を休めながら外を眺めることができた。
夕闇が垂れこめていたが、窓はまだ開いていた。しかし窓枠の上にちょこんとあらわれたアナスタシアの頭は、下までおろされたブラインドに隠され、外からは見えなかった。このブラインドは緑色をした、幾つもの小さな木の羽根板でできており、何度も夏の太陽に当たって色はかすれ、火ぶくれができていた。壺形の真鍮のつまみを回すと隙間が空いて、部屋の中から外がのぞけるようになっている。
しばらく前から読書ができないくらい暗くなっていたのだが、アナスタシアは窓辺の席に座りつづけた。ブランダマー卿が階段を降りてくる音を聞きつけると、通りの景色が見えるように真鍮のつまみを回した。叔母が玄関で滔々と同じお世辞を繰り返すのを聞き、暗闇の中で顔が赤くなるのを感じた。彼女が赤面したのはウエストレイが重要人物にむかってあまりにもぞんざいでなれなれしい口を利くのが癇に障ったからでもある。そして顔を赤くするという自分の愚かさに対して赤面した。正面玄関のドアがようやく閉まり、ガス灯の明かりが階段を降りるブランダマー卿の活力のある姿と、まっすぐで四角い肩に当たった。三千年前、もう一人の乙女が側柱とドアのあいだから、父の宮殿を去るもう一人の偉大なよそ者のまっすぐな広い背中を見ていた。しかしアナスタシアはナウシカアより幸運だった。バイエケス人の船にむかいながら、ユリシーズが後ろを振り返ったという記録はないけれど、ブランダマー卿は振り返って後ろを見たからである。
彼は振り返って後ろを見た。アナスタシアには彼が火ぶくれのできた小さな羽根板を通してまっすぐ彼女の目を覗きこんだように思われた。もちろんまことにつまらない町の、まことにつまらない下宿屋にいる、まことに愚かな女主人の姪である、まことに愚かな娘が、日よけの後ろから彼を見ているなど、彼に推測できようはずがなかった。しかし彼は振り返って後ろを見たのだ。アナスタシアは彼が帰ったあとも半時間あまりその場から動かなかった。またたくガス灯の光りの中に垣間見た厳しく、目鼻立ちの整った顔のことを考えていたのだ。
それは厳しい顔だった。彼女は暗がりの中で目を閉じ、何度もその顔を思い浮かべた。彼女にはその厳しさが分かった。厳しくて――ほとんど残酷ですらあった。いや、残酷ではない。ただ情け容赦ない決意を秘めているのだ。目的を達するために必要ならば残酷さえも辞さない決意を。このように彼女は小説風のやり方で議論を重ねた。ヒロインたるもの、この程度の議論ができなくてどうしようと彼女は思っていた。ヒロインは、どれほど謎めいた顔であっても一目でその仮面をはぎ取り、「涙なしの読み物」(註 イギリスの初等読本)の頁を読むように、そこに書かれた情熱を明瞭に読み取ることができなければ、残念ながらその気高い役割を勤める資格がないのである。彼女、アナスタシアにそのくらいの単純な能力が欠けているはずがあるだろうか。いや、彼女は男の顔つきを一瞬で見定めた。あれは残酷なまでに固く決意している顔だわ。厳しいけれど、でも、なんてハンサムなのかしら!彼女ははじめて戸口で会ったとき、灰色の目が彼女の目とぶつかり、その力で彼女の目を眩ませてしまったことを思い出した。十代の田舎娘にしては驚くべき洞察、驚くべき心理の読み取りである。しかし
ドアが勢いよく開かれ、空想は破られた。ミスタ・シャーノールが部屋に入ってきたとき、彼女は椅子から飛び上がった。
「おやおや!どうなっているんだね。火は焚かず、窓は開けっ放し。お嬢さんはサー・アーサー・ベディバ(註 アーサー王伝説に出てくる忠実な騎士)を夢見て風邪をおめしになる――えらく詩的な鼻風邪じゃないかね」
彼のおしゃべりは石筆をとがらす音のように彼女の気分を不快にした。彼女は何も言わず、脇をすり抜け、後ろ手にドアを閉めると、ぶつぶつ言う彼を暗がりに残して去った。
ブランダマー卿の訪問という興奮は、ミス・ジョウリフを疲労困憊させてしまった。彼女は殿方たちに夕食を持っていき――ミスタ・ウエストレイはその晩ミスタ・シャーノールの部屋で食事をした――アナスタシアにちっとも疲れていないと請け合ったのだが、しかし程なくそんなそぶりもできなくなって、首もたれが左右に張り出した背の高い椅子に、安らぎを求めて避難せざるを得なかった。この椅子は台所の隅に置いてあって、病気とかほかの緊急事態のときにしか使われないものだった。食事の片付けを促す呼び鈴が鳴ったが、ミス・ジョウリフはぐっすりと寝こんでいて、その音が聞こえなかった。アナスタシアは通常は「給仕」をすることを許されていなかったが、疲労の溜まりすぎた叔母を起こしてはならないと、自分でお盆を持って階段を上がった。
「なかなかの美男子ですね」彼女が部屋に入ったとき、ウエストレイがそう言っていた。「しかしそのほかの点ではあまり好ましい印象を持たなかったな。聖堂のことをやけに熱心に話していましたよ。そのあと五百ポンドの寄付をしてくれたのなら、それも大いに結構なんですがね。しかしいくらうっとりしてしゃべっても、それを現実のものにするために半ペニーだって払う気がないんだからどうしようもない」
「あいつは爺さんそっくりだ」とオルガン奏者は言った。
うるう年 二月は二十九日まで
支払いは
「ここらじゃそういっているのさ。今日の午後、さんざん言ってやったよ。まさかブランダマーとは知らなかったから、思い切りこっぴどくやっつけてやった」
汚れた皿や夕食の残り物を盆に集めながらアナスタシアの頬は激しく色づき、胸の中にはさらに激しい感情が渦巻いていた。彼女は懸命に動揺を隠そうとしたが、そうすればそうするほどいっそう動揺は募った。オルガン奏者は彼女の方に視線をむけることなく、じっと様子をうかがっていた。彼は抜け目のない男で、彼女がテーブルを片付けおわるまでに、一時間前、彼によって破られたあの夢の中で誰が主人公を演じていたのか察しをつけてしまった。
ウエストレイはミスタ・シャーノールのパイプからただよってくる煙を片手で払った。
「誰か先代の卿に修復工事の話を持ちかけなかったのかって質問されたので、主任司祭が手紙を書いたけど梨のつぶてだったと言ってやりましたよ」
「手紙は先代の卿に出したんじゃないよ」ミスタ・シャーノールが口をはさんだ。「他でもないあいつに宛てて出したんだ。あいつに出したことを知らなかったのかい?先代のブランダマーに手紙を出したって紙とインクの無駄だってことは皆知っている。そんな馬鹿なことをしたのはわたしだけだよ。一度、オルガン修理の嘆願書を印刷し、名簿の筆頭に署名して欲しいと一部送りつけたことがある。しばらくして十シリング六ペンスの小切手を送ってきたよ。わたしは礼状を書いて、オルガン椅子の脚が折れたら、これで直せますわいと言ってやった。もっともやつのほうが一枚上手だった。小切手を現金に換えようと銀行に行ったら、支払い停止になっていたんだ」
ウエストレイは細くて甲高い声で愉快そうに笑ったが、それがアナスタシアには、あけすけな馬鹿笑いよりいらだたしく感じられた。
「聖堂に七千八百ポンドかかると聞いて躊躇したとき、それならあなたのためにオルガンを何とかしてもらおうと思ったんですよ。わたしはあなたがこの家に住んでいると言ったんです。お会いになりませんかって。『いやいや、今は止めておきましょう』とこう言いましたよ。『別の日に』ってね」
「爺さんそっくりだ」オルガン奏者はもう一度苦々しく言った。「採れるものなら、あざみから無花果を取るがいい(註 マタイ伝から)。しかしブランダマーから金をせしめようとは思うな」
皿を取り上げるとき、アナスタシアは親指をカレーの中に突っこんだことも気がつかなかった。彼女はとにかくその場を離れ、二人の毒舌の聞こえないところへ行き、こっそり隠れて胸のつかえをおろしたくてたまらなかった。ミスタ・シャーノールは部屋を出ようとする彼女にむかってもう一撃を放った。
「じいさんに似ているのは握り屋というところだけじゃない。じいさんは女たらしで悪名高かったが、今度のはそれに輪をかけた女たらしだ。身持ちの悪いやつらさ――どいつもこいつも」
ブランダマー卿がベルヴュー・ロッジによい印象を残せなかったのは確かに不運だった。若い娘は彼の顔つきを厳しく残酷であると判断し、建築家は彼のけちな性格を見抜き、オルガン奏者は断固彼を敵に回す覚悟をしたのだから。そうしたことを何一つ知らずいたのは彼の心の平安にとって幸いであった。いや、もしかしたら、そうしたことすべてを知っていたとしても彼はあまり悩まなかったかも知れない。彼のことを褒める唯一の人間はミス・ジョウリフだった。彼女は一寝入りしたあと顔を赤らめ、しかし元気を回復して起きあがった。そして夕食の食器が洗って片付けられていることに気がついた。
「あらまあ、あなた」彼女はたしなめるように言った。「わたし、寝こんで全部あなたにやらせてしまったのね。こんなことしちゃいけないわ、アナスタシア。起こしてくれればよかったのに」だが肉体は弱し(註 マタイ伝から)。彼女はあくびを隠すために、とっさに手を顔の前に持っていかなければならなかった。しかし彼女の心は本能的にその日の大事件のことへと戻っていった。彼女は穏やかに振り返って言った。「とっても立派な方ね。威厳があって、それでいて愛想がよくて。おまけにとびっきりハンサムだったじゃない」
第九章
こうした注目すべき出来事のあった翌朝、郵便屋がベルヴュー・ロッジに配達した手紙の中に、恐ろしいほど興味をそそる封筒が一通混じっていた。垂れ蓋の上に宝冠模様が黒く小さく押され、表には「カラン、ベルヴューロッジ、エドワード・ウエストレイ様」と太い読みやすい字で書かれていた。それだけではない。左下の隅には「ブランダマー」という署名がはいっていたのだ。たった一語ではあるが、それはあまりにも神秘的な意味に満ち、アナスタシアは胸をときめかせながら手紙を叔母に渡し、建築家の朝食と一緒に上の階へ持って行ってもらった。
「お手紙ですわ、ブランダマー卿から」ミス・ジョウリフは盆をテーブルに置きながら言った。
しかし建築家はただうなっただけで、定規とコンパスを使って忙しく製図に取り組みつづけた。ミス・ジョウリフがかくのごとき重要な書状の内容に燃えるような好奇心を感じなかったとしたら、彼女は女性を超越した存在だっただろう。それに貴人からの手紙をテーブルの上に放っておくのは、彼女にしてみれば、ほとんど神を冒涜するにも等しかった。
朝食を並べるのにそのときほど時間がかかったことはなかったが、それでも例の手紙はつつましい燻製ニシンを覆うブリキ蓋の横に置いてあった(栄光がいかに無価値なものと隣り合っていることか)。哀れなミス・ジョウリフはウエストレイにことの重大さを正しく認識させようと部屋を出る前に最後の努力をした。
「お手紙が来てますよ。ブランダマー卿からだと思いますわ」
「ええ、ええ」建築家は突っ慳貪に言った。「すぐ読みますよ」
こうして彼女は打ちのめされて引き下がった。
ウエストレイの無関心は一部は見せかけでしかなかった。彼は他人はどうあれ、自分は階級という人工的な身分差など意に介さない、農民に感銘を受けないように貴族にも感銘を受けない、そういうところを見せたかったのである。この超然とした無関心はミス・ジョウリフが部屋を出たあともつづいた。彼は人生を真面目に生きようとし、自分に対する義務は少なくとも隣人に対する義務と同じくらい大切だと思っていた。決意は二杯目のお茶まで持続し、そこで彼は封を切った。
拝啓(と手紙は始まっていた)
昨日のお話ではカラン大聖堂の南袖廊(註 原文では北袖廊)の修復に7800ポンドかかるということでした。この費用はわたしが負担しますので、すでに寄付として集めたお金は別の修復目的に回していただきたいと思います。また建物全体を根本的に修復するのに必要な追加費用もすべて差し出す用意があります。サー・ジョージ・ファークワーに連絡を取っていただき、以上の事情を考慮の上、修復計画を見直すようお取りはからい願えないでしょうか。次の土曜日にカランへ参ります。午後五時頃、お宅に伺いますので、そのあと聖堂を見せていただければ幸いです。
敬白
ブランダマー
ウエストレイは手紙を一気に斜め読みした。平凡に一つ一つ字句を追って理解したというより、直感的に内容を感じ取ったのだった。また、小説では普通、重要な手紙は読み返すことになっているのだが、彼はそれもしなかった。ただ手紙を手に持ち、考えごとをしながら思わずそれをくしゃっと丸めこんでしまった。彼は驚き、喜んだ――ブランダマー卿の申し出によって活動の幅がいちだんと広がり、また自分がこのように重要な通知の伝達役に選ばれたことを喜んだ。要するに彼はうれしさと当惑の入りまじった興奮、思いもよらぬ幸運が訪れたとき、よほど強い心の持ち主でないかぎり見舞われる精神的陶酔を感じ、くしゃくしゃの手紙を握り締めたまま、ミスタ・シャーノールの部屋へ降りていったのである。燻製ニシンはおいしそうな匂いをいたずらに朝の空気にまき散らした。
「たった今、びっくりするようなニュースが届いたんですよ」彼はドアを開けながら言った。
ミスタ・シャーノールは不意を打たれることはなかった。ミスタ・ウエストレイ宛にブランダマー卿から手紙が来たことをミス・ジョウリフから聞いていたので、彼は「ほう!」と言っただけだった。その口調には、いとも簡単に平常心を失うウエストレイの落ち着きのなさを哀れむような響きがあった。そしてこの世のいかなる大災難も、彼、ミスタ・シャーノールを驚かすことはないのだと宣言するように「で、どうしたのかね」と付け加えた。しかし興奮したウエストレイは冷や水を浴びせられてもそれをはじき返し、喜悦満面、大声で手紙を読み上げた。
「ふうむ」とオルガン奏者は言った。「別にどうということでもあるまい。七千ポンドくらい、あいつにとっちゃ、はした金だ。それになすべきことをなしたるとき、われらは無益なる僕なり、さ(註 ルカ伝から)」
「七千ポンドだけじゃありませんよ。修復のためならいくらでも出すと言っているんですよ。三万ポンド、四万ポンド、いや、もっと出すかも知れない」
「その金を自分の懐に、なんて思わないかい」とオルガン奏者は言い、眉をつり上げ、ウインクをして見せた。
ウエストレイはいらいらした。
「まったく、あの人がすることに皮肉しか言わないなんて、了見が狭すぎますよ。昨日はけちんぼと言ってけなしました。今日はそれが間違いだったと潔く認めましょう」彼は純粋だが、はなはだしく世間知らずで、そうした人間に特有の過度に几帳面な良心にさいなまれ、後悔の念にかられていたのだ。「とにかくわたしは間違っていました。袖廊の修復費用の話をしたとき、彼が躊躇した意味を完全に誤解していたんです」
「きみの騎士道的精神は大いに賞賛されるべきだ」とオルガン奏者は言った。「意見をころりと変えることができるなんてすごいじゃないか。わたしは最初の意見に固執するよ。口から出まかせを言っているだけさ。金を払う気なんかないか、さもなきゃ何か魂胆があるんだ。わたしはあいつの金なんか船竿の先でつつくのも嫌だね」
「ええ、そうでしょうとも」ウエストレイは小学生のように大げさな皮肉っぽい口調で言った。「オルガンを直すのに千ポンド出すと言っても、あなたは一銭も受け取らないんでしょうね」
「千ポンド出すなんてまだ言ってないぞ、あいつは。もしもそう言ってきたら嫌味を言って追い返してやる」
「そいつは寄付を考えている人には心強い話だ」ウエストレイはあざ笑った。「意地ずくで寄付を申し出なくちゃならないでしょうね」
「さて、わたしはもうちょっと楽譜を写さないとな」オルガン奏者は素っ気なく言い、ウエストレイは燻製ニシンのもとへと引き返した。
このようにミスタ・シャーノールは気前のよい申し出に対して情けないほど感謝の意をあらわさなかったが、カランの他の人々はその例に追従するそぶりも見せなかった。ウエストレイはうれしさのあまり素晴らしい知らせを打ち明けずにはいられなかった。また秘密にしなければならないいかなる理由もなかった。彼は石工頭、教会事務員のミスタ・ジャナウエイ、牧師補のミスタ・ヌートにこのことを告げ、主任司祭の参事会員パーキンにはいちばん最後に話をした。もっとも彼にこそ、いちばん最初にニュースを伝えるべきであったことは言うまでもないけれど。そういうわけで聖セパルカ大聖堂の組み鐘がその日の午後三時に「新しい安息日」を演奏する頃には、町中の人がブランダマー卿の帰還と、大聖堂修復工事費用負担の約束を知ったのだった。大聖堂は誰にとっても大きな誇りであったが、自分の懐から寄付金を出すという、疎ましいことを考える必要がないとき、その誇りはいやがうえにも高まった。
参事会員パーキンは腹を立てていた。彼が午後一時にお昼を食べに帰ってきたとき、ミセス・パーキンはそのことに気がついたが、賢明な女性である彼女は、すぐさま不機嫌の理由を問いただそうとせず、経験の示すところ彼の気持ちをもっともなだめる話題へと会話を誘導しようとした。その中でもサー・ジョージ・ファークワーの歴史的訪問と、主任司祭の提案に対して彼が敬意を示した話は主要な位置を占めていた。ところがこの偉大な建築家の名前を出すと、それを合図に夫は新たな怒りを顔にみなぎらせるのだった。
「サー・ジョージ・ファークワーにはもう少しご本人みずから聖堂工事を監督してもらいたいものだ。彼の代理の、ミスタ、ええと、ミスタ・ウエストレイは、経験不足もはなはだしい。建築の知識も足りないし、恐ろしくうぬぼれた若造で、身の程をわきまえずいつもしゃしゃり出てくる。彼は今朝、実に奇っ怪な手紙を持ってやってきた。なんとブランダマー卿からの手紙だよ」
ミセス・パーキンはナイフとフォークを置いた。
「ブランダマー卿からの手紙ですって」彼女は驚きを隠そうともしなかった。「ブランダマー卿からミスタ・ウエストレイに手紙ですって!」
「そうだよ」主任司祭はつづけた。自分のことばが大きな衝撃を与えたことに満足し、不愉快な気分はいくらか薄らいだ。「その手紙で卿はまず南袖廊(註 原文では北袖廊)修復の費用を負担すると言い、それから建物の他の部分も修復の必要があるなら、その費用の不足分を提供すると申し出たのだ。むろんわたしは上院議員がすることに疑問をさしはさむような真似はしないよ。しかし同時に今回の話の進め方は極めて異例だと言わざるを得ない。このような手紙を主任司祭で、神聖な建物の正式な管理人にではなく、たかが工事監督に送るなんて、失礼きわまりないではないか。わたしとしては全面的に反対し、この申し出をお断りしたいくらいだ」
彼の顔は崇高な義憤の色を帯び、妻にむかって公開の会合で話すようにしゃべった。たとえ天が落ちようとも正義は行わしめよ。参事会員パーキンは厳格なる礼節の道から一歩たりともはずれるわけにはいかぬ。心の奥底では、差し出された贈り物を断るなど、到底不可能なことは分かっていたが、しかし自分のことばのあまりの勇ましさに、初期キリスト教徒がライオンから身を守るための、ひとつまみの香料を風に吹き飛ばしたように、ついみずからの手でブランダマー卿の金を床にたたきつけるさまを思い描いたのだった。
「この申し出はお断りしなければならんと思う」彼は繰り返した。
ミセス・パーキンは夫をよく理解していたし――恐らく彼が自分のことを知る以上に深く理解していた――おまけにこの議論が単に形式的なものに過ぎないことも見抜いていた。どれほど本気で申し出を断るような素振りを見せても、実は彼女がそれを決して許さないことを確信しながら言っているのだ。しかし彼女は相手に合わせて、真剣に賛成するふりをした。
「あなたがためらうのも無理はないわ。あなたを知る人なら誰でも、ためらうのが当然だと思うでしょう。そんな大切な申し出を、あの厚かましい若者から伝えられるなんて、侮辱以外の何ものでもない。それにブランダマー卿自身、いかがわしい評判のある方ですからね、神聖な目的のためとはいえ、彼から何かを受け取ることがどの程度望ましいことなのか分かりはしません。この申し出はお断りするのが正しいのかも知れませんわ。少なくとも時間をかけて考えるべきよ」
主任司祭はこっそりと妻を見た。あっさりと自分の意見が受け入れられたので、やや慌てていたのである。彼は妻ががっかりすることを望んでいた――そして自分の高邁な決意を良識ある議論で揺さぶって欲しかったのだ。
「うむ、それでふと思い出したよ、断るのを難しくしているいちばん厄介な理由を。つまり、その、神聖な目的という点なんだ、自分の判断に疑いを抱いてしまうのは。この贈り物をわたしが断ることで聖堂が損害を被るとしたら、これは考えるのもつらい。断るのはもしかしたら自分自身のいらだちや個人的な動機に屈服するということなのかも知れないね。より尊い義務のためには自分の誇りを捨てなければならない」
彼は最上の説教檀的態度で締めくくり、茶番はすぐに終わった。贈り物は受け取らなければならないこと、ミスタ・ウエストレイについては、ブランダマー卿がかくも不適切な伝達経路を用いたのは彼の仕組んだことに違いないから、しかるべき方法でそのおこがましさを罰すること、そして主任司祭はやんごとなき寄付者に直接感謝の手紙を書くことが合意された。かくして昼食後、参事会員パーキンは「書斎」に引きこもって、そうした場合にふさわしい、大げさな言い回しの手紙を書きあげた。その中で彼はありとあらゆる高潔な動機や美質をブランダマー卿に付与し、きざったらしいことこの上ない祝福を彼の頭に浴びせかけた。お茶の時間にこの手紙はミセス・パーキンによって目を通され添削された。彼女は仕上げに独自のことばを付け加えた。特に前口上には、参事会員パーキンが現場監督から聞いたところによると、ブランダマー卿はある申し出をするために参事会員パーキンに手紙を書きたいとおっしゃったが、まずそのような申し出が参事会員パーキンの意にかなうかどうか、現場監督にお尋ねになったそうですね、という文言を加え、また結語には、この次カランにお出での際は司祭館でおもてなしを受けてくださいますように、と書き添えた。
手紙がフォーディングのブランダマー卿のもとに届いたのは、翌日の朝、遅い朝食を取りながらテーブルの上のコーヒーカップの横にウェルギリウスを開いているときだった。彼はにこりともせず主任司祭の堅苦しい美文を読み、すぐに格別丁重な返事を書こうと思った。それから注意深く手紙をポケットに入れ、暗記しようとしていた農耕詩第一巻の「われらが父祖の神よ、祖国の神々よ、ロムルスよ」に戻った。招待のことはすっかり頭から追い出され、次の週、カランに着くまで思い出されることはなかった。
ブランダマー卿の訪問と聖堂修復に対する申し出は、一週間のあいだ、カランの人が寄ると触ると噂する、お決まりの話題となった。幸運にも彼を見たり、話をした人は、その人となりを議論し意見を交換した。外見から声から物腰まで、どんな些細な点も彼らは逃すことがなかった。この関心は感染力があり、卿をまったく見たことのない人までもが興奮のあまり、卿に通りで呼び止められ、建築家の下宿へ行く道を聞かれたと言い出す始末で、卿があまりにも多くの印象的、かつ信用すべき発言をしているものだから、あの晩、彼がベルヴュー・ロッジにたどり着いたのが不思議なくらいだった。教会事務員ジャナウエイは重要人物との会話の機会を逃し、悔しがることしきりだったが、見知らぬ男の灰色の目が彼をナイフのように刺し貫くのを感じたとか、自分は御前様が聖歌隊席に入るのを止める振りをしただけで、相手の堂々たる要求態度を見て、自分の直感が正しいことを確かめたかったのだ、などと強調した。ほかでもねえ、ブランダマー卿とお話しているこたあ、しょっぱなから分かっていたのさ、と彼は言った。
ウエストレイはこの一件の重要性にかんがみ、ロンドン行きを決意した。ブランダマー卿の寄付によって可能になった修復計画変更について、サー・ジョージ・ファークワーと相談をするためである。しかしミスタ・シャーノールは下宿に残って、ミス・ジョウリフの追想や憶測や賞賛を聞いていた。
はじめてこのニュースに接したときは無関心を装ったにもかかわらず、オルガン奏者は誰かが来ると驚くくらいみずから進んでこの話題を取り上げた。ミス・ジョウリフに対しても彼女がブランダマー卿のことを話しているかぎり、いつものようないらいらした様子は微塵も見せなかった。彼はそのこと以外話ができないのではないかと、アナスタシアは思った。沈黙したり話題を変えて、彼の話をさえぎろうとすればするほど、いっそう辛辣な攻撃が卿に対して再開されるのだった。
聖堂修復のために寄付をし、しきたりを踏みはずしてしまったこの不幸な貴族に何の関心も示さない唯一の人間はアナスタシアその人だった。心の広いミス・ジョウリフでさえ、このときばかりは姪の冷淡さを咎めずにはいられなかった。
「ねえ、あなた。立派なすぐれた行いをそんなふうに無視するなんて、若い人であろうと年寄りであろうと、いけないことじゃないかしら。ミスタ・シャーノールは神様の思し召した境涯に不満を持っているみたいだから、褒めるべきものを褒めないことがあったとしても驚かないわ。でも若い人はそうはいかない。わたしが若いときに誰かがウィドコウム大聖堂の修復費用を寄付したら――特に貴族が寄付したら――きっとその――新しい服を買ってもらったみたいな喜びを、それに近いものを感じると思うわ」彼女は「きっとその方がわたしに新しい服を買ってくれたみたいな」と言いそうになったのを別の表現に変えたのだった。いくら説明に過ぎないとはいえ、貴族が自分に新しい服を買ってくれるなど、大それた不適切なことのように思われたのだ。
「わたしなら有頂天になったと思うわ。でもねえ、あの当時はみんな先見の明がなくて、修復なんて考えもしなかった。わたしたちは日曜日ごとにとっても座り心地のいい椅子に座っていたものよ。クッションと膝布団がついていて、通路は板石敷き――表面がすり減った普通の板石敷きで、陶磁のタイルなんか全然使っていないの。タイルは見栄えはするけど、いつも滑りそうな気がしてねえ。あんなのはないほうがいいわ。固すぎるし、ぴかぴかしすぎ。あの頃教会にあったのはとても時代遅れなものばかりよ。みんながまわりの壁に血縁の銘板をかけたり、黒大理石の石版の上に白い小箱を載せたものとか、壺とか、天使の頭像とかを置いてるの。わたしの席の真向かいには、名前は忘れたけど、柳の木の下で泣いている可哀想な貴婦人の絵がかかっていたわ。去年の冬に町の会館で若い男の方が『教会を美しくするために』っていう講演をして、その中で言っていたけど、確かにああしたものは神聖な場所にふさわしくないわね。あの方は『壁面の火ぶくれ』と呼んでいたわ。でもわたしの若い頃はそれを取っ払おうなんて誰も言わなかった。そのためのお金を出す人がいなかったからだと思うわ。それが、ほら、ご親切にもまだお若いブランダマー卿が気前よく寄付をしてくださって。きっとカラン大聖堂はもうすぐ見違えるようになるでしょう。あの講演者も言っていたけど、わたしたち礼拝のときはしなだれるような姿勢をしちゃだめなのよ。あの方は『しなだれる』ってことばを使っていた。ベーズと膝布団は取り払われるでしょうねえ。でもちょっとでいいから何かを席に残しておいて欲しいわ。むき出しの木の上に座ると、ときどき身体が痛くなるんですもの。こんなこと、世界中であなたにしか言えないけど、でも本当にときどき身体が痛くなるのよ。それから通路に陶磁が敷かれたら、わたし、転ばないようにあなたの腕にすがりつくわ。ブランダマー卿がわたしたちのためにこうしたことをみんなしてくださるっていうのに、あなたときたらちっとも感謝してないんですもの。若い娘にあるまじき態度よ」
「叔母さん、わたしにどうしろというの。町の人に代わって、ありがとうございました、なんて、みんなの前で言うわけにもいかないじゃない。そっちのほうがよっぽどあるまじきことだわ。聖堂が叔母さんの言うようなひどいことにならなければいいわね。わたしは古い記念の品が大好きよ。それに椅子は木がむき出しになっているより、『しなだれる』ことのできるほうがいいわ」
そう言って彼女は笑い飛ばした。しかしブランダマー卿の話をさせることはできなかったものの、彼女が彼を思い浮かべることはもっと増えたのであり、あの重大な土曜日の午後のあらゆる出来事が昼夜を問わず夢の中で何度も何度も上演されていたのである。彼が気取らず直裁にブランダマー卿その人であることを打ち明ける序曲から、彼が振り返る終幕の瞬間――彼女はブラインドの背後に隠れていて、そこにいることは分かるはずがないのに、その彼女の眼をとらえるように彼が視線を投げかけてきたあの瞬間まで。
ウエストレイは状況の変化に伴って練り直され拡充された修復計画と、ブランダマー卿宛の手紙を手に、ロンドンから戻った。手紙の中でサー・ジョージ・ファークワーは気前のいい献金者に面会の日取りを指定してもらえないだろうかと書いていた。サー・ジョージはカランまで出むいて卿に挨拶をし、この件に関して直接相談しようと思っていたのである。ウエストレイは一週間のあいだブランダマー卿との土曜日午後五時の約束を楽しみにし、聖堂をどのような道順で案内しようかと慎重に思案をめぐらせていた。ところが五時十五分前にベルヴュー・ロッジに戻ると、訪問者はすでに彼を待っていた。ミス・ジョウリフはいつものように土曜日の会合に出ていたが、アナスタシアがウエストレイに、ブランダマー卿が半時間以上もお待ちだと告げたのである。
「お待たせして申し訳ありません」ウエストレイは部屋に入りながら言った。「約束の時間を勘違いしたのかと思いましたが、でもお手紙には確かに五時と書いてありますよ」彼はポケットから封を切った手紙を取り出して差し出した。
「勘違いしたのはわたしのほうです」ブランダマー卿は自分の指示を読んで、笑みを浮かべながら認めた。「四時と言ったような気がしたんですがね。しかし手紙を一、二通書く暇ができて幸いでしたよ」
「聖堂に行く途中で投函できますよ。ちょうど郵便列車に間に合うでしょう」
「いや、明日にします。同封するものがあるのですが、今手元にないので」
彼らはそろって聖堂にむかった。ブランダマー卿は通りを渡るとき後ろを振り返った。
「とても風格のある建物ですね。ちょっと手を入れれば住み心地もよくなるんだろうけど。何かできることがあるか、代理人と話をしなければならないな。このままでは領主としての評判にかかわりますからね」
「ええ、面白い特徴がたくさんありますよ」ウエストレイが答えた。「この建物の来歴はもちろんご存じでしょうね――つまり以前は宿屋だったということですが」
彼は同伴者と一緒に家のほうを振り返ったが、一瞬何かがミスタ・シャーノールの部屋のブラインドの背後で動いたような気がした。しかしきっと目の錯覚に違いない。家にはアナスタシアしかいないし、彼女は台所にいる。彼は外に出るとき、お茶に遅れるかも知れないと大声で彼女に言ったのだった。
ウエストレイは聖堂のなかを案内したり説明したりしながら、陽の光りが落ちるまで一時間半あまりの時間を心ゆくまで楽しんだ。ブランダマー卿は見るものすべてに、婉曲語法でよく言われるところの「知的関心」を示し、極めて豊かな建築学的知識を、隠すでもなく、ひけらかすでもなく、ごく普通に口にした。ウエストレイは質問こそしなかったものの、どこでそんなことを覚えたのだろうといぶかった。視察が終わるころには、彼は技術的な問題に関して、素人にむかってではなく、対等な専門家に語るようにしゃべっていた。彼らは中央塔の下でしばらく立ち止まった。
「わたしがとりわけ感謝しているのは」とウエストレイが言った。「寛大にも全てをわたしたちの自由裁量に任せてくださったことです。これで塔に手をつけることができます。この上の部分が大丈夫とはとても思えません。アーチは建造当時のものとしては異常に幅広で、厚みがないんですよ。お笑いになるかも知れないけど、わたしはときどきアーチが直してくれって叫んでいるような気がするんです。特に南側のアーチ、上の方の壁にぎざぎざの割れ目ができているやつは。たまに聖堂や塔のなかにひとりでいると、アーチのことばが聞き取れるような気がします。『アーチは決して眠らない』って言っているんですよ。『われわれは決して眠らない』って」
「ロマンチックですね」とブランダマー卿は言った。「建築はことばが石に変じたものだ、という昔の格言がありますね。きっとあなたは相当な詩人なんでしょう」
彼はしゃべりながら禁酒家の痩せてやや青ざめた顔と高い頬骨を見た。ブランダマー卿は冗談を言わず、めったに笑うこともないと思われていたが、もしもその場にウエストレイ以外の人間がいたなら、卿のことばのいたずらっぽい調子と、目尻に浮かぶ面白がるような表情に気がついたかも知れない。しかし建築家は何も気づかず、少し赤くなりながらこう話しつづけた。
「ああ、そうかもしれませんね。建築はたしかに人に霊感を与えますね。わたしがはじめて書いた詩、というか、少なくともはじめて活字になった詩はチュークスベリ修道院の後陣を謳ったものです。グロスター・ヘラルド紙に掲載されました。いつかこのアーチのことも何か書きたいですね」
「是非そうしてください」とブランダマー卿は言った。「そしてわたしに一部送ってください。この場所には詩人が必要です。それにアーチのことを詩に書くほうがアーチ形の眉毛について詩を書くよりずっと無難ですものね」
ウエストレイはまた赤くなって胸ポケットに手を入れた。うっかり書きかけの詩を机の上に置いたままにして、ブランダマー卿や他の誰かに見られたのだろうか。いや、大丈夫だ。彼は通常の手紙とは異なる、縦方向に折った紙の、鋭い角を指先に感じた。
「よろしかったら時間もあるようですし、屋根の部分をご覧にいれましょうか」彼は話題を変えて言った。「袖廊の交差穹窿の頂点を見ていただいて、今取りかかっている作業の説明をしたいんです。あそこはいつ行っても薄暗いんですが、カンテラがあると思います」
「もちろん喜んで」彼らは北東の基柱内部に造られた螺旋階段を登った。
教会事務員のジャナウエイは視察する彼らから安全な距離を置いたところをうろうろしていた。彼は聖堂が閉まる前に、日曜日の「準備」をしておくという名目のもとに忙しく立ち働いていたのだ。一週間前、ブランダマー卿の行く手に立ちはだかったことを思い出して、できるだけ目につかないようにしていたが、その実、彼はあたかも偶然であるかのように卿に出会い、あんな振る舞いに及んだのは何も知らなかったからだと言い訳がしたくてたまらなかったのである。だがそんな言い訳の機会は都合よく訪れなかった。二人は天井に登り、教会事務員は扉口に鍵をかけようとしていた――ウエストレイは自分用の鍵を持っていたのだ――するとそのとき、誰かが身廊をこちらへやって来る音が聞こえた。
脇に楽譜をどっさり抱えたミスタ・シャーノールだった。
「やあ、あんたか!」彼は教会事務員に言った。「ずいぶん遅くまでいるんだな。自分で鍵を開けて入らにゃならんと思っていたのに。一時間前に帰ったんじゃなかったのかい」
「今晩は片付けにいつもより手間どってね」彼は急に話をやめた。頭上の足場のどこかから微かな音が聞こえてきたのだ。彼は声をひそめて話しつづけた。「ミスタ・ウエストレイが卿を案内してるんでさあ。今屋根のところですよ。聞こえるでしょう」
「卿だって?どこの卿かね。あのブランダマーの野郎のことか」
「ええ、そう。でも野郎なんて言っていいんですかい。あの方は卿ですからね。だからわたしは卿とお呼びして野郎なんて言いませんよ。そんなに敵意をむき出しにして、あの方が何をしたって言うんです?どうしてここであの方を待ってパイプオルガンのことを話さないんです?もしかしたら太っ腹な気分になっていてパイプオルガンを修理するとか、あんたがしきりに話しているちっこい送風器を買ってくれるかもしれんじゃねえですか。どうしていつも歯をむき出すんですかねえ――いや、見せようにも、あんたには本物の歯がたくさん残っちゃいないから、こりゃあもののたとえっちゅうもんだがね――たまには他の人と同じようにしちゃあどうです?わたしが思うには、あんたは年寄りなのに若者ぶろうとしている。貧乏なのに金持ちぶろうとしている。そこがいけない。そのせいであんたはみじめな気分になり、酒でまぎらせようとする。わたしの忠告を聞いて、他の人みたいに振る舞いなさいよ。わたしはあんたより二十も年寄りだが、二十歳の時より遙かに人生を楽しんどるよ。今はお隣さんも連中の癖もわたしを楽しませてくれるし、パイプの味もよくなった。若いときゃさんざん馬鹿なまねをしでかすが、年をとりゃ、そんなこともない。あんたはわたしに遠慮なくしゃべるから、わたしもあんたに遠慮なくしゃべるよ。わたしは遠慮のない人間だし、誰もおそれるこたあないんだ。卿だろうが、野郎だろうが、オルガン弾きだろうがね。まあ、この老いぼれの忠告を聞くんだね。明るく構えて卿にお仕えし、新しいパイプオルガンを買ってもらいなさいよ」
「くだらない!」ミスタ・シャーノールはジャナウエイの態度に慣れてしまっていて、腹も立てなければ注意も払わなかった。「くだらない!ブランダマーなんてどいつもこいつも大嫌いさ。ドードー鳥みたいに絶滅すりゃいいんだ。絶滅してないって保証はないんだけどね。いいかい、あの気取って歩くクジャク野郎は、あんたやわたしと同じくらいブランダマーを名乗る権利を持ってないんだ。この富というやつにはまったくむかつくな。今じゃあ教会や博物館や病院を建てることができない人間は価値がないと思われている。『みづからを厚うするがゆゑに人々なんぢをほむる』(註 詩篇から)金を持ってりゃひたすら賞賛され、なければ鼻も引っかけられん。ブランダマーなど全員墓に埋められてしまえばいい」彼は細いしゃがれ声をまたもや頭上の穹窿天井に響かせた。「経帷子の代わりに雲形紋章を巻き付けてな。あいつらの忌々しい紋章なんかにゃ石をぶつけてやりたいよ」彼は袖廊の窓高くに描かれた海緑色と銀色の盾を指さした。「日の照るときも、月明かりの差すときも、あれはいつもあそこにある。ここで満月の夜、コウモリに演奏を聴かせるのが楽しみだったんだ、あれがいつも張り出しをのぞきこんでいて、わたしから離れようとしないことに気づくまでは」
彼はどさりと楽譜の山を座席に置くと聖堂を飛び出した。どうやら酒を飲んでいたらしい。教会事務員も同時にその場を抜け出した。大声で発せられた意見を屋根の上の二人に聞かれ、彼もそれに同調していると思われることを恐れたのだ。
ブランダマー卿は聖堂扉口でウエストレイに別れを告げた。彼は仕事の都合でフォーディングに戻らなければならないと、お茶の誘いを断った。
「別の日の午後、また聖堂を見せてください。よろしければ手紙で日取りをお知らせします。たぶんまた土曜になるでしょう。平日は今のところ用事が詰まっていますので」
教会事務員ジャナウエイは聖堂からさほど離れていないガヴァナーズ通りにすんでいた。この名の由来は誰も知らなかったが、ドクタ・エニファーは革命が起きて、カランが議会派によって守られていたとき、この近所に
鎧戸のペンキ塗りはもちろんガヴァナーズ通りではちょっとした大行事である。そこの住人のうち、少なからぬ人々が船乗りか、または漁業用小型帆船の持ち主で、幸運の女神が微笑んで無事に引退し、もはやペンキを塗るべき船がなくなると、今度は鎧戸やドアや窓枠がそれに取って代わることになる。割れ目から染み出す松ヤニや火ぶくれしたワニスの生暖かいにおいがガヴァナース通りに夏の再来をはじめて知らせる晴れた朝には、六十代、七十代、なかには達者に八十代を迎えた人々がペンキ入れと刷毛を手に、自分の住まいの木造部分に新たな装いを施す姿が見られるだろう。
彼らは気だてがよくて、開けっぴろげで、生き生きとして、腰が大きく、真鍮ボタンの紺色のピージャケットを身につけている。無敵の喫煙家、つきることのない物語の紡ぎ手である彼らはジャナウエイを快く仲間うちに迎え入れて久しかった――彼らの考えでは、教会事務員と墓堀は見えざるものを知る専門家みたいなもので、近い将来最後の航海に出る際、いや、なかにはすでに船首に出航旗を掲げている人もいるのだが、この航海の際には、水先案内人を勤めてくれるのだから、なおのこと彼は歓迎されたのだ。
ごろ石のあいだから生えている銀梅花が家の並びの真ん中に立つ小屋の正面に丹念に這わせられていて、ドアに掛かる真鍮の板は旅人と何も知らない人のために「T・ジャナウエイ、寺男」が中に住んでいることを教えてくれた。ブランダマー卿とウエストレイが別れてから二時間ほどあとの土曜日午後八時頃、正面を銀梅花に覆われた小屋のドアが開けられ、教会事務員が敷居に立ってパイプをふかしはじめた。中からは陽気な赤みを帯びた光があふれ、料理のにおいがぷんと漂いだした。ミセス・ジャナウエイが夕食の支度をしていたのである。
「トム」と彼女は呼びかけた。「ドアを閉めてご飯にしましょう」
「ああ」と彼は答えた。「すぐ行くよ。でもちょっとだけ待ってくれ。こっちに歩いてくるのが誰だか、確かめたいんだ」
よそ者と一目で分かる男がむこう端から通りに入りこんでいた。半月が出て、その明かりで男が家を探しているのが分かった。男は道を左右に横切りながら、ドアに記されている番号をのぞきこんでいた。近づくにつれ、教会事務員は男が痩せていることや、ゆったりしたコートかケープを羽織っていること、それが夕方の海風にひらひらとはためいていることに気づいた。次の瞬間ジャナウエイはよそ者がブランダマー卿であることを知り、じゃまにならぬように本能的に一歩退いた。しかし開いたドアがとっくに通行者の注意を引いていた。彼は立ち止まり、朗らかにその家の主に挨拶した。
「すてきな夜だね。でも空気が冷たくて、お宅のぽかぽかした暖かい部屋がとても心地よさそうに見えるよ」彼はしゃべりながら教会事務員の顔を思い出し、こうつづけた。「おや、わたしたちはすでにお会いした仲ですね。一週間前、聖堂でお目にかかりましたよね」
ミスタ・ジャナウエイは予期せぬ出会いに少々たじろぎ、しどろもどろの挨拶をした。ブランダマー卿を聖歌隊席に入れまいとした、あの出来事はまだ記憶に新しく、彼は泡を食って弁解しようとした。
ブランダマー卿はにっこりと好意的な笑みを浮かべた。
「私を止めようとしたのは当然です。そうしなければ職務怠慢ですからね。礼拝が進行中とは思わなかったのです。さもなければ入ったりしなかったでしょう。あのことは気になさらないでください。これからもカラン大聖堂に行ったときは、席に案内してくださいよ」
「あなたの席は探す必要がありませんや、御前様。参事会員パーキンと同じように、ちゃあんと決まってるんで。裏側に紋章がくっきりと描かれとります。ご心配には及びません。みんな内務規定に定めてあるんです。御前様が席にお着きになるときは、主教様のときと同じ敬礼をいたします。『二回腰をかがめること。職杖は右手に持ち、左手を添えること』これ以上丁寧にはできねえんですよ。というのは三回礼をするのは皇族に対してだけなんで。わたしが勤めているあいだ、皇族なんて一人も聖堂に来たことがありませんがね――それだけじゃないんです。覚えていらっしゃらねえでしょうが、先代のブランダマー卿もあなたのお父様とお母様が埋葬された日から、お出でになったことがございません」
ミセス・ジャナウエイは夕食テーブルを拳でたたいた。彼女は夕ご飯ができたと言ったのに、戸口に立っておしゃべりをつづける夫にあきれていた。しかし会話を聞いているうちに、しだいに見知らぬ男の正体が明らかになり、カランの誰もがその名を口にする人物を見たいという気持ちを抑えることができなくなった。彼女は戸口へいってお辞儀をした。
ブランダマー卿はコートに重ねたはためくケープを左肩越しに後ろへ放った。教会事務員にはその仕草が外国人ぽく思われ、日曜の夜、なめるように見ている雑誌、イラストレイティド・ロンドン・ニュースのイタリア・オペラの板目木版画を頭に浮かべた。
「もう行かなければ」訪問者は身震いして言った。「あなた方をここに立たせておくわけにはいきません。今夜はやけに冷えますからね」
そのときミセス・ジャナウエイは急にむこう見ずな気分におそわれた。
「中に入ってしばらく暖まっていかれてはどうです」と彼女は口をはさんだ。「料理の匂いさえお気になさらなければ、火も燃えていますから」
教会事務員は妻の大胆さに一瞬震え上がったが、ブランダマー卿はさっそく招待を受け入れた。
「ありがとうございます。列車が出るまでしばらく休ませてもらえるととても助かります。料理の匂いがするからといって謝ることはありませんよ。すごく食欲をそそるじゃありませんか。特に夕食の時間には」
彼はまるで夜の食事はいつも質素で、豪華な晩餐など生まれてこのかた聞いたこともないというような話し方をした。五分後、彼はジャナウエイ夫婦とテーブルに着いた。テーブルクロスは荒い手織り布だったが清潔だった。ナイフとフォークは古い緑の柄がついており、主料理は牛の胃だったが、客は食事を大いに楽しんだ。
「人によっちゃあハチノスやセンマイがうまいなんて思っているのもいますがね」教会事務員は空になった皿を見ながら思いにふけるように言った。「しかしわたしの好みから言えば、ミノにはかないませんな」彼が大胆にも料理に対する私見を披露したのは、客が目の前のごちそうを心ゆくまで食したとき、天の邪鬼でもないかぎり、どんな主人も感じる満足感に促されてのことだった。
「そうですとも」とブランダマー卿は言った。「何と言ったってミノが最高ですよ」
「胃袋そのものも大事ですけど、料理法も同じくらい大事なんですよ」ミセス・ジャナウエイは自分の腕前を無視されたと思い、腹を立てて言った。「最高の胃袋があっても料理が下手じゃどうにもなりません。作り方はいろいろあるんですが、ミルク少々とネギで作るのがいちばんだと思います」
「それに勝るものはありませんね」ブランダマー卿は同意した――「それに勝るものはありません」――そしてそれとなくこうつづけた。「メースの小枝を入れたことはありますか」
ミセス・ジャナウエイはそんな料理法は聞いたことがなかった。その点をつっこんで聞かれていたら、ブランダマー卿も知らないと言っていただろう。しかし彼女はこの次試してみると約束し、そのときはまたご一緒いただければ光栄なのですけれど、とこの尊敬すべき客人に言った。
「土曜日の晩だけなんですよ、ミノが手にはいるのは」彼女は話しつづけた。「それ以上頻繁に出回らないのは、かえってありがたいんです。お金がありませんから。トマスみたいにいい旦那が持てて、わたしくらい幸せな女はいませんわ。お金のかからない人なんです。飲むのはお茶だけなんですよ、御前様。でも土曜の夜は贅沢して、少しだけ胃袋料理を食べるんです。とても精がつきますし、夫は日曜日のおつとめがとても大変ですから、ちょうどいいんです。御前様が胃袋料理をお好みで、土曜日の晩またこちらにお出でになって、わたしたちに名誉をほどこしてくださるなら、いつだって準備してお待ちしていますわ」
「ご親切なお招き、とても感謝します」ブランダマー卿は言った。「おことばに甘えさせていただきますよ。カランに来るのは土曜日がいちばん多いのですよ、というか、最近はたまたまそうなんですけど」
「世の中にゃ貧乏で哀れな人間がおります」と教会事務員は考え深げに言った。「わたしら夫婦は貧乏だが幸せですよ。しかしミスタ・シャーノールは貧乏で不幸せです。『ミスタ・シャーノール』とわたしは言ってやるんです、『親父が十ペンスのビールを飲みながらよく言ったもんだ。排水口に押しこまれた貧乏と、そいつを踏みつける、木の義足の男に乾杯ってね。でもあんたは貧乏を排水口に詰めこまねえし、まして踏みつけもしない。いつも取り出して風にさらし、思い悩んで自分を悲しませている。あんたが悲しいのは貧乏だからじゃない。貧乏だと思ってそのことを口にしすぎるんだ。あんたはわたしらほど貧乏じゃない。ただやたらと不平が多いんのさ』ってね」
「ああ、オルガン奏者のことですね」ブランダマー卿は尋ねた。「今日の午後、あなたと聖堂でしゃべっていたのは彼ではないですか」
教会事務員はまたもやまごついた。ミスタ・シャーノールの暴言と、ブランダマー一族への呪詛が聖堂に響き渡ったことを思い出したのだ。
「そうなんで。かわいそうにオルガン弾きはちょっと興奮してしゃべっとりました。ときどきあんな具合になっちまうんです。不満やら、それを紛らすビールのせいで。そういうときは大声を出すんですよ。あいつの並べた世迷い言がお耳に入ってなけりゃいいんですが」
「ああ、とんでもない。ちょうど建築家と話しこんでいたんです」とブランダマー卿は言ったが、その口調からジャナウエイは、ミスタ・シャーノールの声が具合悪くも遠くまで届いていたことを知った。「何を言っているのかは分からなかったけど、ずいぶんいらだっているようですね。数日前に聖堂でおしゃべりをしましたよ。そのとき彼はわたしが誰か知らなかったんですけど。でもわたしの一族にあまりいい感情を抱いていないようでした」
ミセス・ジャナウエイはこういうときは思慮あることばをさしはさむべきだと思った。「御前様にむかっておこがましいことを言うようですが、あの人のことはほっておかれるといいですよ。あの人は夫にむかっても同じように悪口を言うんです。オルガンのことで頭が変になっていて、新しいやつを買うか、少なくともカリスベリにあるような水仕掛けの送風器を買ってもらうのが当然だと思っているんです。無視してください。ミスタ・シャーノールの言うことなんか、カランの人は誰も気にしやしません」
教会事務員は妻の分別に驚いたが、それが相手にどう取られるか不安だった。しかしブランダマー卿は優雅に頭を下げて、賢明な助言に感謝の意をあらわし、こうつづけた。
「カランにおかしな人がいませんでしたか。自分は権利を剥奪されているが、本来はわたしの地位にいるべきなのだと考えていた人が――つまり自分こそはブランダマー卿であると考えていた人が」
その質問はごくさりげなく発せられ、彼の顔は哀れむような笑みをかすかに浮かべていた。しかし教会事務員はミスタ・シャーノールの「気取って歩くクジャク野郎」とか、「本物のブランダマーなんてもういないんだ」などということばを思い出し、ひどくそわそわした。
「その通りで」彼は一瞬間をおいて答えた。「御前様の前じゃこんな話ははばかられますが、そんなおかしな考えに取り憑かれた老いぼれもいました。そういや、ミスタ・シャーノールもあいつと同じ下宿に住んどります。きっと左巻きがうつったんですな」
ブランダマー卿は無意識に煙草を取り出したが、女性がいることに気づいて箱に戻し話をつづけた。
「おや、ミスタ・シャーノールと同じ下宿ですか。その話はもっと聞きたいですね。言うまでもありませんが、興味がありますから。名前は何というんです」
「マーチン・ジョウリフですよ」教会事務員は間髪を入れず答えた。逸話を語るチャンスに、思わず熱心な口調になった。そしてウエストレイに語ったように、マーチンとマーチンの父、母、娘の物語を逐一ブランダマー卿に繰り返したのだった。
夜もずっと更けた頃になって物語はようやく終わった。地元の警官がガヴァナーズ通りを幾度か巡回したが、遅いにもかかわらず明かりがついている窓を見て驚き、ミスタ・ジャナウエイの家の前に来ると立ち止まった。ブランダマー卿は汽車で帰る予定を変えたのだろう。カラン駅の改札口は数時間前に閉ざされ、支線を走るおんぼろ列車は車庫でその蒸気
「おもしろい話ですね。それにあなたはお話が上手だ」彼はそう言って立ち上がり、コートを着た。「楽しいことには必ず終わりがあるのですが、お二人には近いうちにまたお会いしたいと思います」彼は夫婦と握手し、酒場から持ってきたビールのジョッキを、「排水口に詰めこまれた貧乏と、それを踏みつける義足の男に乾杯」と言って飲み干し、出て行った。
その一分後、もう一度見廻りに戻った警官は、ゆったりしたコートを着てケープを軽く左肩にかけた中背の男とすれ違った。見知らぬ男は小唄を口ずさみながら元気よく歩き、地上のことなどすっかり忘れてしまったかのように、顔を上げて星と風の吹く空を見ていた。真夜中のガヴァナーズ通りによそ者がいるというのは、窓に明かりが灯っていることよりさらに驚くべきことで、警官は呼び止め、用むきを確かめようかと思ったが、そこまで強く出ようと決心するまもなく、足音は遠くに消えようとしていた。
教会事務員は自己満足に浸り、話し手としての成功に得意になっていた。
「ありゃあ、賢い、話の分かる人だよ」彼はそう言って妻と一緒に床に就いた。「いい話がどういうものか、ちゃんと知っていなさる」
「いい気におなりじゃないよ、あんた」と彼女は返事した。「請け合ってもいいわ、御前様はあの話の中にあんたが話した以上のことを見て取っていらっしゃるんだから」
第十章
ブランダマー卿の惜しみない支援のおかげで修復工事は拡充し、ウエストレイは一度ならずロンドンのサー・ジョージ・ファークワーのもとへ相談に出むかなければならなかった。ある土曜日の晩、そんな訪問からカランに帰ってきたとき、彼は自分の食事がミスタ・シャーノールの部屋に用意されていることを知った。
「夕ご飯を一緒に食べてくれるだろうと思ったんだよ」とミスタ・シャーノールは言った。「どういうわけか分からないが、冬が始まり、日暮れが早くなると、いつも気が滅入るんだ。時間が経つと何でもなくなって、冬の夜長や暖かい暖炉の火は好ましいくらいなんだがね。もっとも十分な火をたけるくらい金があればの話だが。しかしはじめのうちはちょっぴり憂鬱になるんだ。そういうわけだから食事につきあってくれたまえ。今夜は暖かい火もあるし、きみのために特別に手に入れた流木もある」
食事のあいだ、どうということのない世間話がかわされたが、オルガン奏者は何か別のことを考えているらしく、ウエストレイは一度か二度、相手がうわの空で返事をしているような気がした。実際彼は別のことを考えていた。というのも彼らが暖炉の前に落ち着き、ちらちらと揺らめく流木の炎にお決まりの賞賛のことばが呈されると、ミスタ・シャーノールはためらうように咳払いをしてこう切り出したからである。
「今日の午後、どうも妙なことが起きたんだ。夕べの祈りが終わって帰ってみると、なんとブランダマーがわたしの部屋で待っているじゃないか。明かりも灯していなかったし、火も焚いていなかった。火は遅くに焚いたほうが、きみと暖かく過ごせると思っていたんだ。やつは窓辺の席の端っこに座っていた。くそっ、地獄に落ちろ!――(ミスタ・シャーノールが冒涜のことばを発したのは、そこがアナスタシアのお気に入りの席で、他の人が使うことは認めがたかったからである)――しかしわたしが入ってくると、もちろん立ち上がったよ。そして調子のいいことをとうとうとまくし立てるのさ。部屋に入りこんだことは心からお詫びする。ミスタ・ウエストレイに会いに来たのだが、残念なことによそにお出かけになっている。勝手だがミスタ・シャーノールの部屋でしばらく待たせてもらうことにした。ミスタ・シャーノールと是非、お話したいことが一つ二つあったのだ、ってな具合だよ。わたしはおべっかが大嫌いだということは知っているだろう。それにあいつがどんなに嫌いだったか――いや、嫌いかってことも(と彼は訂正した)。しかしどうも具合が悪くてなあ。ほら、彼はもう実際に部屋の中に入りこんでいたわけだし、人は自分の部屋にいるときは、他人の部屋にいるときみたいに不作法な真似はできないからね。それに明かりもつけず、火も燃やさず、わたしを待っていてくれたということで、気の毒したという気持ちも多少あった。もっともどうしてあいつが自分でガスの火を入れなかったのか、理由が分からんが。だから不本意ではあるが丁寧にお相手をしてさしあげたのだよ。で、さあ、これでやつを追い払えるぞと思ったときに、折悪しく家に一人残っていたアナスタシアがお茶を出してもいいかと聞きにきたというわけさ。分るだろう、わたしの苛立ちが。しかしやつにお茶を一杯いかがですと訊かないわけにもいかないじゃないか。まさかうんと言うとは夢にも思わなかったが、やつは招待を受けやがった。そんなわけで、なんてことだろう!われわれは旧知の仲みたいにお茶を飲みながら和気藹々おしゃべりしたってわけさ」
ウエストレイは愕然とした。ミスタ・シャーノールはつい先日、ブランダマー卿の申し出を拒絶しなかったと彼を非難したばかりなのに、このお茶の会が示すように、憎しみと悪意の高邁な原則からまるで逸脱してしまったことがさっぱり理解できなかった。彼の人生経験はいまだにごく限られたものでしかなく、嫌悪や反感というものはたいてい現実的というより理論上のものにすぎず、個人的な接触において緩和されたり、すっかり消滅しがちなものであること――つまり憎しみの炎を燃え立たせつづけること、あるいは気持ちのいい態度で和解を求める人に面とむかって無礼なことを言いつづけるのはひどく困難であることが分からなかったのである。
おそらくミスタ・シャーノールはウエストレイの顔に驚きを読み取ったのだろう。彼はいっそう弁解するような調子でこうつづけた。
「それどころじゃないんだ。やつのせいでわたしはえらくやっかいな立場に立たされてしまった。確かに面白い話をする男だな。音楽について大いに語り合ったのだが、驚くほどこの方面に造詣が深いし、正しい趣味の持ち主だ。どこであんな教養を身につけたのか見当もつかない」
「建築についても同じ印象を持ちましたよ」ウエストレイは言った。「聖堂を視察しはじめたときは先生と生徒という関係でしたが、視察を終えるころには、わたしよりも聖堂のことを詳しく知っているのじゃないかと、落ち着かない気持ちにさせられました――少なくとも考古学的なことに関しては」
「ほう!」とオルガン奏者は無関心そうに言った。自分の体験を話したくてたまらない人は、他の人がどんなにわくわくするようなことを言っても、無関心な態度を取るものだ。「やつの趣味は異常に洗練されていた。前世紀の対位法の作曲家に精通していて、わたしの作品もいくつか知っているのさ。不思議なことがあるものだ。やつが言うには、どこかの聖堂で――どこだったか忘れたが――サーヴィスを聴き、あんまり感動したのでビラを見たら、シャーノール変ニ長調だったというのだ。われわれが話を始めるまで、わたしの作品だとは気づかなかったらしい。あのサーヴィスはもう何年もしまいこんだままだな。オクスフォードでギボンズ賞に応募したときの作品でね。グロリアの中にフーガを取り入れ、主音のペダル音で終わるんだ。きみも気に入るだろう。あれは探し出しておかなければならんな」
「ええ、それは聴いてみたいですね」ウエストレイは強い関心があるからというより、話し手が一息入れるあいだ、間を持たせるためにそう言った。
「聴かせてあげるとも――聴かせてあげるとも」とオルガン奏者はつづけた。「ペダル音がすばらしい効果を出していることが分かるだろう。それでわれわれの話題はだんだんとオルガンのことに移っていった。聖堂ではじめて彼に会った日にたまたまオルガンの話をしたんだ。もっとも普段はきみも知ってのとおり、わたしはオルガンのことは一言もしゃべらないことにしている。あのときはオルガンのことにさほど通じているようには思えなかったが、今じゃ知らぬことはないという感じだ。だからわたしは何をするべきか、自分の意見を言ったのだよ。で、ふと気がついたらやつが口をはさんできて『ミスタ・シャーノール、あなたのお話には大変関心があります。とても理路整然としていて、わたしのような門外漢にも理解ができます。ファーザー・スミスがはるか昔に作った、この美しい音色の楽器が壊れたまま、いつまでも放置されているのは嘆かわしいことです。聖堂を修復してもオルガンがなければ意味がありません。ですので修理の細目と、他にそろえるべき品目を一覧にして書き出してくれませんか。あなたの提案はすべて実行されるとお考えください。とりあえず、あなたがおっしゃっていたウオーター・エンジンと新しい足鍵盤をすぐ注文して、費用をお知らせいただければと思います』わたしは呆気にとられてしまったよ。口がきけるようになったときには、彼の姿はもうなかった。わたしはどうすればいいのか、さっぱり判らなくなった。あの男はいけ好かないね。やつの申し出は冷ややかに拒絶するつもりだ。あんな男の恩を受けるなんてまっぴらだ。きみだってわたしの立場だったら断るだろう?すぐさま断固拒否の手紙を書くだろう?」
ウエストレイは馬鹿正直な性格で、人の言ったことばをそのまま信じる傾向があった。彼はミスタ・シャーノールの自主独立の精神がいかに気高いものであれ、それがためにこれほど気前のいい寄付が断られるのはまことに残念なことだと思った。そしてオルガン奏者の決心を翻させようと、思いつくかぎりの反論を必死になって繰り広げ、かき口説いた。この申し出は善意から出たものである。ミスタ・シャーノールはブランダマー卿の人柄をきっと誤解しているのだ――ブランダマー卿には下心があるというミスタ・シャーノールの考えは間違っている。善意以外のどんな動機があり得るだろうか。それにミスタ・シャーノールがどれほど個人として拒否しようとも、あれだけ修理の必要が歴然としたオルガンなのだから、結局は直されるに決まっているではないか。
ウエストレイは熱心に語りかけ、自分の雄弁がミスタ・シャーノールに及ぼした効果を見て満足した。議論によって相手の考えを改めさせるというのは極めてまれにしか起きないことで、自分の組み立てた議論が、少なくともミスタ・シャーノールの決意に影響を与えるくらい説得的であったことを知り、彼は得意になった。
うむ、きみの言うことにも一理あるかもな。考え直してみよう。今晩は断りの手紙を書かないよ。断るのは明日だってできる。とりあえず新しい足鍵盤を手配し、ウオーター・エンジンを注文しよう。カリスベリでウオーター・エンジンを見て以来、いつかはカランにも一つ必要だと思っていたんだ。あれは是非とも注文しよう。ブランダマー卿に払ってもらうか、修復基金全体から差し引いてもらうかは後で決めればいい。
この結論は最終的決定ではないとはいえ、確かにウエストレイの説得の勝利だった。しかし当初ブランダマー卿の申し出を一切受け付けまいとしたミスタ・シャーノールの愚直な自主独立を咎めたのは、はたしてどの程度正しいことだったのだろうと、いささか疑問に思われるところもあり、心から満足したわけではなかった。ミスタ・シャーノールがこの件にためらいを感じているなら、自分、ウエストレイはそのためらいを尊重すべきではなかったか。あまりにも説得力のあることばでそれを押さえこんだのは正しいことへの干渉ではなかったろうか。
彼の疑いはミスタ・シャーノール自身がこの精神的ジレンマに激しく悩まされていたという告白を聞いても鎮まることはなかった。オルガン奏者はこの難問に心をかき乱され、神経を静めるためにウイスキーをコップになみなみと注いだと打ち明けたのである。同時に彼は二三冊のノートと大量の紙切れを棚から降ろし、彼の前のテーブルに広げた。ウエストレイは思わず何だろうとそれらを見つめた。
「本気でまたこれを調べなければならんよ」とオルガン奏者は言った。「最近はえらく怠けていたんだが。これはマーチン・ジョウリフが残した大量の書類とメモだ。かわいそうにミス・ユーフィミアはこれを調べる勇気がなかったんだ。そのまま焼き捨てようとしていたのを、わたしが『おや、そんなことをしちゃいけない。わたしによこしなさい。調べて保管する価値のあるものが混じってないか見てあげよう』と言ったのだ。それでこれを手に入れたのだが、なんだかんだ邪魔が入って、ろくに調べちゃいないのさ。死んだ人の書き物に目を通すのはいつだってわびしい気持ちにさせられるが、生涯をかけた仕事として、これが残されたすべてだというときは、そのわびしさはひとしおだよ――マーチンの場合は失われた仕事とでもいうんだろうな。日の光が見えはじめたちょうどそのとき、あの世に召されたんだから。『我らは何をも携へて世に来たらず、また何をも携へて世を去ること能はざればなり』(註 テモテへの手紙から)このことばが頭に浮かぶとき、わたしは金や土地のことよりもささやかなもののことを考える。お金よりも大切にしていた恋文とか、その人の死と共に手がかりが失われた証拠品とか、戻ってきて片付けるはずだったのに、戻ることなく未完に終わった仕事とか、もっと言えば、気に病んでいた未払いの請求書とかね。死はすべてを変貌させる。ありきたりのものを哀切なものに変えるんだ」
彼は一瞬、間を置いた。ウエストレイは相手が急に感傷的になったことに驚き、何も言わなかった。
「うむ、わびしいものだよ」オルガン奏者が再びつづけた。「この書類に書いてあるのはみんな雲形紋章――海緑色と銀色のことなんだ」
「すっかり頭がいかれていたんでしょうね」ウエストレイは言った。
「他の人ならそう言うだろうが」オルガン奏者は答えた。「しかしいろいろ考えると、この中には単に狂気とばかりはいえないものがありそうな気もするんだ。今はそれくらいしか言えないが、生きていればそのうち真相が分かるだろう。このあたりには奇妙な言い伝えがあってね。いつ頃から言われはじめたのか知らないが、ブランダマーの家系には謎があるというのだ。家督を受け継いだ者には、実はその権利がないといわれている。それだけじゃない。大勢の人が謎を解こうとして、中には有力な手がかりをつかんだ人もいたそうだが、しかしあと一息というところで、何かが彼らの命を奪うんだ。マーチンに起こったのはそれなんだよ。わたしは彼が死んだ日に彼と会った。『シャーノール』と彼はわたしに言ったよ。『おれがあと四十八時間生きられたら、あんたは帽子を脱いで、おれに御前様って言っているかもしれないぜ』ってね。
しかし彼も雲形紋章にはかなわなかった。彼は死ななければならなかったのだ。だからわたしがそのうちぽっくり行ってしまっても驚いちゃいけないよ。ま、そういうことさえなければ、真相を探り当て、近い将来、ここにちょっとした変化を引き起こして見せるがね」
彼はテーブルの前に座り、しばらく紙束を見ているふりをした。
「マーチンも気の毒だったな」彼はまた立ち上がり、棚を開け酒瓶を取り出した。「きみも飲むだろう、ええ?」とウエストレイに訊いた。
「ありがとうございます。でも結構ですよ、わたしは」ウエストレイはその細い声にこめられるかぎりの軽蔑に近い響きをこめた。
「一口だけだよ――飲みたまえ!わたしは一口だけ飲まなければやってられん。この紙切れを調べるとひどく疲れるんだ。こいつを読むのは思っていた以上に重要なことなのかもしれん」
彼は大コップに半分ほど酒を注いだ。ウエストレイは少し躊躇したが、良心と幼少時のピューリタン的教育が彼に口を開かせた。
「シャーノール。それは捨ててしまいなさい。その酒瓶はあなたを誘惑する悪魔ですよ。男らしく捨ててしまいなさい。あなたを見ていると黙っていられないのです。堕落していくのを腕組みしてじっと見ているわけにはいかないのです」
オルガン奏者は素早い一瞥を彼にくれ、生の酒を大コップになみなみと注いだ。
「いいかね。最初はグラスに半分だけのつもりだったが、今はまるまる一杯飲もうと思う。忠告に感謝してな!堕落していくか!その横柄な態度もろとも地獄に堕ちろ!礼儀正しい口がきけないなら、誰か別の人の部屋で夕飯を食えばいい」
ついかっとなったウエストレイは冷静な批判という観覧席から悪口合戦という闘技場に降りてしまった。
「ご心配なく」ウエストレイはとげとげしく言った。「二度とお付き合いすることはありませんから安心なさい」彼は立ち上がり、ドアを開けた。出て行こうとむきを変えたとき、寝室にむかうアナスタシア・ジョウリフが廊下を通った。
彼女が通り過ぎるのを見てミスタ・シャーノールはいっそう頭に血が上ったらしい。彼は手ぶりでウエストレイにじっとしているよう伝えると、ドアを閉め直した。
「糞食らえ!」と彼は言った。「きみを引き留めたのは、これを言うためだ。糞食らえ!ブランダマーなんか糞食らえ!みんな糞食らえ!貧乏なんか糞食らえ!裕福も糞食らえ!オルガンのためだろうがなんだろうが、あいつの金なんか触るのもいやだ。さあ、出て行っていいぞ」
ウエストレイは上品に育てられ、口汚く罵られたり、下品で無礼な個人攻撃を受けることには慣れていなかった。野卑な形容詞、現代の作法ではしばしば大目に見られる「えげつない」とか「胸クソ悪い」といった表現、まして忌まわしい呪いことばには生まれつき身をすくませる質だった。だからミスタ・シャーノールの悪口は彼を深く傷つけたのである。動揺したまま寝床に就き、取り返しのつかないまでに友情が壊れたことを悲しみ、不当な非難に憤慨し、それでいてこうしたことがわが身に降りかかったのは、己の不注意のせいではなかったかと自責の念にかられ、まんじりともせず夜の半分を過ごした。
朝になっても気分はさわやかにならずしょげ返っていたのだが、朝食の最中に太陽が輝きだし、彼はより悲観的でない方向で自分の置かれた状況をとらえはじめた。ミスタ・シャーノールとの友情は修復できないほど壊れてはいないかも知れない。もしも壊れてしまったとしたら残念だ。彼はその生活態度の欠点にもかかわらず、老人が好きになっていたからである。全面的に非難されるべきは、彼、ウエストレイのほうだった。他人の部屋に呼ばれておきながら、その人にむかって説教したのだ。青二才の彼が老人である相手に説教したのだ。それが善意のなせる行為であったことは本当である。つらいけれども義務だと思ってしゃべったに過ぎない。しかし言い方がまずかった。あまりにも押しつけがましかったのだ。話し方に思慮を欠いたため、もっともな忠告があだになってしまった。はねつけられることは覚悟の上で謝ろう。下に降りてミスタ・シャーノールに謝罪し、必要ならもう一方の頬もぶたれてやろう。
良き決断はそれを実行する固い意志を伴う場合、乱れた心に幾分かの落ち着きを回復せずにはおかないものだ。良き決断がその穏やかな効き目を失うのは、一定間隔で繰り返す悪行と後悔の恐るべきシーソーが停まってしまい、心がもはや生における不変の正しさの可能性を信じられなくなったときである。このシーソーは必ず漸を追って均衡を失うものなのだ。悪への傾きがますます優勢になり、美徳への回帰はますますまれに、かつ短くなる。そのあとは神を敬う心の持続しないことにあきらめを覚え、良き決断は単なる心の反射運動となって慈悲深い影響力をなくし、心に平安をもたらすことがなくなるのである。こうした状態は中年より前に生じることはまれで、ウエストレイは若く、ことのほか良心的であったから、高尚な意図を抱くと、胸の中に強い落ち着いた気分がじわりじわりと広がっていった。そのときドアが開いてオルガン奏者が入ってきた。
かんしゃくの爆発と一夜の深酒がミスタ・シャーノールの顔にその跡を残していた。表情はやつれ、心臓が弱いせいでできている目の下の隈はいちだんと黒く、いちだんとふくれあがって見えた。決まり悪そうに中にはいると、足早に建築家に近づき、手を差し出した。
「許してくれ、ウエストレイ」と彼は言った。「昨日の晩ははしたない口をきいてしまった。きみの言ったことは正しいよ。きみに敬意を払う。もっとずっと前からきみのように諭してくれる人がいたらよかったんだが」
差し出された手はそうあるべきほど清潔ではなかったし、やかましい目で見れば爪もきちんと切られていなかったが、ウエストレイはそんなことに気づきもしなかった。震える老人の手を取り、無言のまま暖かく握り返した。彼は口がきけなかった。
「われわれは仲よくしなければならんね」少し間を置いてオルガン奏者は言った。「仲よくしなければならんね。というのは、わたしはきみを失うわけにはいかないからだ。つきあいは長くないが、きみはこの世でたった一人の友達なんだ。あきれた告白だとは思わんかね」彼は力なくか細い声をあげて笑った。「この世に他に友達はいないのだ。昨日の晩言ってくれたことはいつでもまた言ってくれ。忠告は多ければ多いほどいい」
彼は腰をおろした。これ以上、場に緊張感が漂うことに耐えられず、会話はぎこちないながらも、より個人的でない事柄に移っていった。
「昨日の晩、話したいことが一つあったんだ」とオルガン奏者は言った。「気の毒にミス・ジョウリフは金に困っている。そんなことはわたしには一言も――誰にも言おうとしないが――しかしわたしはたまたまそれが事実であることを知っている。本当に困っているんだ。慢性的な金欠状態。われわれもみんなそうだが、彼女の場合は深刻だよ――壁際に追いつめられ、身動きもならん。彼女を苦しめているのはマーチンの最後の借金だ。生き血を吸い取る商人どもがうるさく彼女につきまとうが、彼女はやつらにくたばっちまえと言ってやる勇気がない。もっとも彼らだって彼女には一銭だって返す責任がないのは知っているのさ。彼女はマーチンの借金が返せないかぎり、あの花と毛虫の絵を持っている権利がないと考えている。あれを売れば金になるからね。覚えているだろう、ボーントン・アンド・ラターワースが五十ポンド払うと言ったことを」
「ええ、覚えていますよ。馬鹿な連中だ」
「まったく馬鹿な連中だよ」とオルガン奏者は答えた。「しかし現にそういう申し出があったとなると、われらが気の毒な女主人は結局絵を売ることになるだろう。『そのほうが彼女にとってはいい』ときみは言うだろうし、常識がひとかけらでもあれば、五十ポンドでも五十ペンスでも、とっくの昔に売り払っていただろう。しかし彼女には常識なんてないし、あれを手放すとなれば彼女は自尊心をずたずたにされ、苦悩のあまり熱を出すに違いない。そこでわたしは、いくらあれば急場をしのげるか、手を尽して探ってきたんだが、たぶん二十ポンドもあれば切り抜けることができると思うんだ」
彼はウエストレイが口をはさむことを半ば期待しているかのようにしばらく黙っていたが、建築家が何も意見を言わないので、次のようにつづけた。
「分からなかったんだよ」彼はおどおどと言った。「きみがここに長く住みつづけ、こうした話にも強い関心を抱くようになるかどうか。わたしは自分で絵を買い取ろうと思っていたんだ。ここに置いておけるように。ミス・ユーフィミアにお金を贈り物として渡すのはだめなんだ。絶対受け取ろうとしないからね。彼女のことはよく知っているから分かるのさ。でも絵と引き替えに二十ポンドを差出し、これからもずっとここに置いたままで、お金ができたときに買い戻せるんだと教えてやれば、天の恵みとその申し出に飛びつくだろう」
「そうですねえ」ウエストレイは疑わしそうに言った。「騙そうとしているなんて思われやしないですか。他の人が五十ポンド出すと言っているのに、二十ポンドで絵を売らせるのは、ちょっと考えるとなんだか変な気がしますが」
「いや、そんなことはない」オルガン奏者は答えた。「ほら、これは本当の売買じゃない。彼女を助けるためのほんの口実に過ぎないんだから」
「ご丁寧にわたしに意見をお求めくださいましたが、思うに、それ以外の点では問題はないと思います。それにミス・ジョウリフのことをそんなに気にかけていらっしゃるなんて、とても立派だと思います」
「ありがとう」オルガン奏者はためらいがちに言った――「ありがとう。そう取ってくれると思っていたよ。もう一つちと困っていることがあるんだ。わたしは赤貧洗うが如しでね。しみったれみたいに一銭も使わず暮らしているが、しかしそれは使おうにも金がなくて、貯金もできないからなんだ」
ウエストレイはミスタ・シャーノールがどうやって二十ポンドという大金をかき集めるつもりなのだろうと、さっきから不思議に思っていたのだが、それについては何も言わないほうが賢明だろうと判断した。
そのときオルガン奏者は意を決して本題に切り込んでいった。
「どうだろう。きみ、一緒に買う気はないかね。わたしは預金口座に十ポンドある。きみがもう十ポンド出してくれたら、絵を共同購入できる。ミス・ユーフィミアはそう遠くない将来、きっと買い戻そうとするから、いずれにしろたいした出費じゃないと思うが」
彼は話をやめてウエストレイを見た。建築家はぎょっとした。彼は慎重かつ用心深い性格で、生まれつきの貯蓄癖は、いかなる不必要な出費も厳しく咎められるべきだという信念と織り合わさって、いちだんと強固なものにされていた。聖書が彼にとって来世の礎であるように、細かく家計を記録し、どんなに少額であっても金を貯金にまわすことが彼にとってのこの世の礎だったのである。注意して生活を切り詰めたおかげで、給金は少ないながら、鉄道会社の社債券にすでに百ポンド以上の投資ができるほどになっていた。半年ごとのわずかな利息小切手の受け取りをひどく大切に保管し、「グレート・サザン鉄道」のレターヘッドの入った封筒に、ある種の威厳と金銭的安心感を見いだしていた。これはときどき株主総会の代理委任状や告知を彼に送り届ける封筒だった。最近預金通帳を調べたところ、もうじき新たに百ポンドを投資に回せそうなことが分かり、彼は胸にいっぱいの希望を抱いて、ここ数日のあいだ、どの株を選ぶべきだろうかと思いを巡らしていたのである。一社の社債に大金をつぎこむことは資産運営上好ましくないと思われたのだ。
資産をはなはだ磨り減らすこの突然の提案はすっかり彼を狼狽させた。それは確かな担保もなしに十ポンドを貸し与えるようなものだった。まともな人間ならこんなへたくそな絵が担保になるとは誰も考えはしない。ぶよぶよした緑の毛虫は朝食のテーブル越しに見たとき彼をあざけって身をくねらせたように思えた。ミスタ・シャーノールの頼みを断ることばが喉元まで出かかった。お偉方が金を貸すのを断るとき、誰もが使う同情のこもった、しかし裁判官のように断固たる調子のことばが。そうした機会にとりわけよく使われる、悲しげだがきっぱりした口調というものがある。それは借り手に、金を出したいのはやまやまだが、道徳的高みに立って判断するなら、今のところ断らざるを得ない、という趣旨を伝えるはずのものである。公共の福利のことを考えなくてすむのなら、すぐにでも頼まれた額の十倍だって出すのだが。
ウエストレイはこれと同じようなことを言おうとしていたのだが、オルガン奏者の顔を一瞥し、そのしわの中にこの上なく痛ましい不安が刻みこまれているのを見て、決心を揺さぶられた。彼は昨夜のけんかのこと、そして今朝、ミスタ・シャーノールが謝罪し、彼より年若い男の前で謙虚に振る舞ったことを思い出した。彼は二人のよりが戻ったことを思い出した。一時間前、よりが戻せるなら喜んで十ポンド払おうと思ったではないか。友情が回復した感謝のしるしに、この貸し付けにはやっぱり賛成したほうがいいのではないか。考えてみたらあの絵は立派な担保になるかも知れない。誰かが五十ポンドを払おうとしたくらいなのだから。
オルガン奏者にはウエストレイの心の変化が分らなかった。ただ気乗り薄そうな最初の印象だけを心に留め、ひどくそわそわしていた――絵を買う動機がミス・ユーフィミアに対する親切だけだとしたら、不思議に思われるくらいそわそわと。
「確かに大金だね。分っているよ」彼は低い声で言った。「きみにこんなことを頼むなんて、わたしもすごく嫌なのさ。でも、これはわたしのためにするんじゃない。わたしは今まで自分のために一銭だって物乞いをしたことはないし、これからも貧民収容施設に行くまでは、そんなことをするつもりはない。迷っているなら、すぐ答えなくてもいい。じっくり時間をかけて考えてくれ。ただできるものなら、ウエストレイ、助けて欲しいんだよ。今、絵をこの家からなくしてしまうのは何とも惜しい」
熱のこもったその話し方はウエストレイを驚かせた。ミスタ・シャーノールは単に親切というだけでなく、何か企みを持っているのだろうか。あの絵はやっぱり価値があるのだろうか。彼は部屋の反対の壁に近づき、安っぽい花と毛虫をじっと見つめた。いや、そんなわけはない。この絵には逆立ちしたって価値はない。ミスタ・シャーノールがあとをついてきて、彼らは並んで窓の外を眺めた。ウエストレイはほんの束の間、迷いを感じた。人情と、そしておそらく良心も、ミスタ・シャーノールの願いに応じるべきだと彼に語りかけた。警戒と貯蓄本能は、十ポンドが手元の全資金の少なからぬ一部であることを思い出させた。
雨の後の明るい日差しがさしてきた。路面には水たまりが光り、店の窓にかかるひさしには水滴の列がきらめいている。砂地の道は日に照らされて暖かい湯気を立てていた。彼らの下でベルヴュー・ロッジの正面ドアが閉まり、縁の広い麦わら帽に、プリント地のドレスを着たアナスタシアが、足取り軽く階段を下りていった。その輝かしい朝、二人の男が上の窓から見ているとも知らず、バスケットを抱え市場へさっそうと歩く彼女は、あらゆるもののなかでもっとも輝いて見えた。
その瞬間ついに人情はウエストレイの頭の中から節約を追い出したのだった。
「いいでしょう」と彼は言った。「是非二人で絵を買いましょう。ミス・ジョウリフとの交渉は任せます。今晩五ポンド紙幣を二枚お渡しします」
「ありがとう――ありがとう」オルガン奏者は大いにほっとした。「いつでも都合のいいときに買い戻せるとミス・ユーフィミアに言っておくよ。彼女が買い戻す前にわれわれの一人が死んだら、そのときは生き残ったほうの所有物だよ」
このようにしてその日、ミス・ユーフィミア・ジョウリフを一方の当事者とし、ミスタ・ニコラス・シャーノールおよびミスタ・エドワード・ウエストレイを他方の当事者とし、両者のあいだに名画売買の契約が成立したのである。緑の毛虫が隅にのたくる派手派手しい花の絵に、競売の木槌が鳴ることはなかった。そしてボーントン・アンド・ラターワース商会はミス・ジョウリフから、故マーチン・ジョウリフ所蔵の絵画は売ることができないという、丁寧な断りの手紙を受け取った。
第十一章
年老いたカリスベリ主教が亡くなり、新しいカリスベリ主教が任命された。この人選は低教会派にいささか悔しい思いをさせた。というのは新主教のウイリス博士は確固たる信念を持つ高教会派だったからである。しかしその信心深さには定評があったし、キリスト教的寛容と相手を思いやる慈愛に満ちていることはじきに理解された。
ある日曜日、朝の礼拝が終わってミスタ・シャーノールがボランタリーを演奏していると、一人の少年聖歌隊員がこっそりと小さな螺旋階段を上がり、オルガンのある張り出しに姿をあらわした。ちょうど彼の先生が幾つかの音栓を引っ張り出し、ストレッタに入ろうとしているときだった。オルガン奏者は階段を上る少年の足音を聞かなかったので、突然白い法衣を目にして飛び上がるほどびっくりした。手も足も一瞬持ち場を離れ、危うく曲が止まってしまうところだった。しかしそれは一瞬のこと。彼は気を取り直し、フーガをその論理的帰結へと導いていった。
それから少年が口を開いて「参事会員パーキンさんから伝言です」とやりはじめたのだが、とたんに中断させられてしまった。オルガン奏者が彼に容赦のない平手打ちを見舞ったからである。「ボランタリーの演奏中にこっそり階段を上がってくるなと、何度言ったら分かるんだ。幽霊みたいに隅っこから出てくるから肝をつぶしたじゃないか」
「すみません、先生」少年はべそをかきながら言った。「そんなつもりじゃ――まさか――」
「まったくおまえは、まさかって真似をしてくれるよ」ミスタ・シャーノールは言った。「さあ、もうめそめそするな。若者の肩に分別ある頭は生えぬ、か。二度とやるんじゃないぞ。ほら、六ペンスやろう。伝言を聞かせてくれ」
六ペンスはカランの少年たちがめったに手にすることのない大金で、この贈り物はギレアデの香油よりもすみやかに少年を慰めた。
「参事会員パーキンさんから伝言です。聖具室でお話がしたいとのことです」
「すぐ行くよ。楽譜を片付けしだい、すぐ行くと伝えてくれ」
ミスタ・シャーノールは急がなかった。午後の演奏のために聖詩篇と典礼聖歌を机の上に開いておかなければならなかったし、朝の礼拝用のアンセム集をしまい、夕べの礼拝用のアンセム集を取り出す必要があったのだ。
かつてこの教会には優れた楽譜集を買う余裕があった。ボイ(註 十八世紀英国の作曲家)の初版申しこみリストには――その人数の少なさにボイ博士が猛烈な屈辱を感じるリストだが――「カラン大聖堂主任司祭兼創設会員(六部)」という記載が今でも見られる。ミスタ・シャーノールは硫酸紙で装丁され、最大限余白をたっぷり取った、偉大なボイの楽譜をこよなく愛した。ページをめくるときの乾いた音も大好きだったし、簡略譜のように一度に九つの五線が読める、古風な音部記号も大好きだった。彼は記憶を確かめるために、一週間の曲目一覧を見た――ワイズ作曲「わが栄えよ、醒めよ」。いや、これは第二巻じゃなくて第三巻に載っているやつだ。間違った巻を取り出したぞ――この楽譜集はよく知っているのに何をしているんだ。背表紙の子牛の粗革がぼろぼろだ!さびのような赤い革くずが彼の外套の袖にくっついていた。これでは人前には出られぬと、さらにしばらく時間をかけてそれを払い落とした。参事会員パーキンは聖具室で待たされていらいらし、ミスタ・シャーノールがあらわれるなり、とげとげしい口調で挨拶した。
「呼ばれたらもう少し早く来てもらいたいね。今は特に忙しいんだから。少なくとも十五分は待ったぞ」
それこそミスタ・シャーノールが意図していたことだった。彼は主任司祭のことばに少しも嫌な顔をせず、ただこう言った。
「失礼しました。十五分も経ってはいないと思いますが」
「ふん、無駄話はやめよう。きみに伝えたかったのは、カリスベリ主教が来月十八日の午後三時に、この大聖堂で堅礼式を行うことになったということだ。われわれは聖歌隊つきの礼拝を行わなければならない。きみにはだいたいでいいから演奏曲案を提出してもらいたい。わたしがいいかどうか点検するから。特に注意すべきことが一つある。主教が身廊を歩くとき、それにふさわしい行進曲をオルガンで演奏しなければならないが――わたしがよく文句を言っている古臭いやつじゃなくて、本当に堂々とした、メロディの判り易いのにしてもらいたい」
「ああ、それなら簡単ですよ」ミスタ・シャーノールはおもねるように言った。「ヘンデルの『見よ、英雄は還りぬ』ならぴったりでしょう。オッフェンバッハのオペラの中にも、手を加えれば使える曲がありますな。ちゃんと感情をこめれば実に耳に快い作品ですよ。フルオルガンで『死の舞踏』をゆっくり弾くこともできます」
「ああ、『マカベウスのユダ』の中の曲だね」主任司祭は思いがけず相手が自分の意見に従ったので、少しだけ機嫌を直した。「ふむ、わたしの意向を理解しているようだ。それじゃこの件はきみに任せるよ。ところで」と彼は聖具室を出るとき振り返って言った。「さっき礼拝の後で弾いていた曲、あれは何かね」
「ただのフーガですよ。カーンバーガーの」
「そのフーガというやつばかりを演奏しないでもらいたいね。学問的見地からはどれもすばらしいことに間違いないが、大多数の人にはただ混乱しているようにしか聞こえん。わたしと聖歌隊が威厳を持って退出しようとするとき、後押ししてくれるというより足かせになっている。厳かな礼拝の最後にふさわしい悲哀と威厳のこもった曲がほしいのだが、同時に聖歌隊席を出て行くときに、足取りを合わせられる、リズムのはっきりしたやつがいい。こんなことを言っても気を悪くしないでくれたまえ。だがオルガンの実用的な側面が最近は非常になおざりにされている。ミスタ・ヌートが礼拝をするときはどうだっていいが、わたしのときは頼むからフーガはやめてくれ」
カリスベリ主教のカラン訪問は重大事件で、ある程度の事前の計画と準備を必要とした。
「主教にはもちろんわたしたちと昼食をしていただかなくては」ミセス・パーキンが夫に言った。「あなた、もちろん昼食にお誘いになるわね」
「ああ、当然じゃないか」と参事会員は答えた。「昨日、昼食のお誘いの手紙を書いたよ」
何食わぬふうを装うとしたが、あまりうまくいかなかった。それほど大切な用件を妻に相談もなく手紙に書いて出したのは、許しがたい無作法ではなかったかと心配になったからである。
「あらまあ、あなた」彼女は応じた――「あらまあ!少なくともことば遣いくらいはきちんとなさったでしょうね」
「ふん!」今度は彼がいささかいらだつ番だった。「主教に手紙を書いたことがないとでも思っているのかい」
「そんなことを言っているんじゃないわ。こういう招待というのは、妻が出すものと決まっているのです。主教が育ちのいい方なら、その家の奥方が書いたのじゃない昼食のお誘いにびっくり仰天なさるわ。少なくともそうするのがしきたりなのよ、育ちのいい方のあいだでは」
「育ちのいい」などという恐るべきことばを繰り返し強調するなど、主任司祭に口論する気があったなら宣戦布告のきっかけともなりかねなかったが、彼は平和を愛する男だった。
「おまえの言うとおりだね」と彼は穏やかに答えた。「ついうっかりしたよ。主教が大目に見てくれることを期待しよう。昨日の午後、主教が来ると公式の通達を受けて、大急ぎで書いたんだ。ほら、おまえは外出中だったし、わたしは手紙の集配に間に合わさなければならなかったから。人間は偉い人に取り入ろうとして何をするかわかったものじゃない。集配に間に合わなかったら、ずうずうしい他の誰かが先に主教を招待することだってありうるじゃないか。もちろん、このことはおまえに伝えるつもりだったのだが、つい失念してしまったのだよ」
「あらまあ」彼女は気持ちが半分しかおさまらず、舌鋒鋭く言った。「わたしたちの他に主教をお招きする人なんかいるかしら。司祭館を除いて、カランのどこでカリスベリ主教がお昼を召し上がるというの」この答えることのできない謎をかけて、ようやくくすぶっていた怒りの火が消えた。「きっとあなたはそうするのが一番いいと思ってなさったんでしょうね。それにずうずうしい俗物連中が大嫌いなのはわたしも同じ。ちょっとでも地位のある人を見つけると、つかまえようとするんですもの。さあ、主教にお会いしていただく方の人選をしましょう。少人数のほうがいいわね。少ないほうが敬意がこもっているように見えるから」
彼女は根っから他人の美点や知性を認めようとせず、恩恵が全員にゆきわたるくらいたっぷりあっても出し惜しみするという表面的で狭量な心の持ち主だった。だから主任司祭とミセス・パーキンの他には、かくも高貴な人物と交際するにふさわしい人間はほとんどいないということがはっきり示されるように、主教との面会に招かれる人は少人数でなければならなかったのだ。
「まったく賛成だ」主任司祭は主教を招待するというみずからの無分別が宥恕されたようだと、ほっと胸をなでおろした。「出席者は何よりも厳選されていなければならない。無論、少人数でいくしかないと思うね。主教との面会にお誘いできるような人間はもともと少ししかいないんだから」
「そうねえ」彼女は両手の指を使って名望家連を数え上げているようだった。「まずは――」彼女は突然あることを思いついてことばを切った。「そうだわ、もちろんブランダマー卿をお誘いしなければならないわ。教会のことにあれだけ強い関心をお示しですもの、きっと主教にお会いになりたがると思うわ」
「実にいい思い付きだ――言うことなしの名案だよ。教会に対する卿の関心を深めることになるだろうし、放浪したり、ボヘミアンみたいな暮らしの後で、正しい階層の人々とお付き合いするのは、あの方にとってもいいことだろう。卿についてはありとあらゆる奇怪な噂が流れているね。工事監督のミスタ・ウエストレイとか、あの方の地位にはまったくふさわしくない連中と仲よくしているという話だ。ミセス・フリントがたまたま裏通りの貧しい女性を訪問したんだが、あの方が教会事務員の家に一時間以上もいて、あまつさえそこで食事もしたと言っていたよ。食べたのは何と胃袋料理だっていうじゃないか」
「じゃあ、主教に会うのはあの方にとってきっといいことだわ」と夫人は言った。「それでわたしたちを入れて四人。あとはミセス・ブルティールをお呼びしてもいいわね。旦那のほうは誘うことないわ。がさつで見ていられないもの。それに主教はビールの醸造業者になんかお会いになりたくないでしょう。奥様一人だけを招待してもちっともおかしかないわ。昼間はお仕事の邪魔になるでしょうからって、決まり文句を使ってやればいいのよ」
「それで五人か。六人にしたほうがいいだろう。あの建築家とかミスタ・シャーノールを誘うのはまずいだろうな」
「あなた!何を考えているの。絶対だめです。そんな人を呼ぶなんてとんでもありません」
主任司祭がこの叱責にすっかりしゅんとなって縮こまったものだから、妻の態度は少し軟化した。
「お誘いになるのは結構よ。でもそんな席に呼ばれても、ばつの悪い思いをするだけでしょう。人数を偶数にしたいならヌートを呼ぶのはどうかしら。あの人は紳士だし、礼拝堂つき牧師で通用するし、お祈りを唱えることもできるわ」
このようにして参加者は決まった。ブランダマー卿は招待を受け入れ、ミセス・ブルティールも招待を受け入れた。牧師補はわざわざ招待するには及ばなかった――彼はただ昼食に来いと命じられただけだった。しかしそこまでは順調に進んだのに、予期せぬ事態が発生した――主教が昼食に来られないと言うのである。彼は参事会員パーキンに丁重な歓迎を受けることができず残念だと言った。しかし用事があって、カランで過ごす時間はすべてそれに当てなければならない。実はほかの人と昼食の約束をしたのである。司祭館には礼拝開始の三十分前に行くつもりだ、とこう連絡してきたのだ。
主任司祭と妻は「書斎」に座っていた。司祭館北側の暗い部屋で、窓外のしめったガマズミの低木と、室内のお粗末な鳥の剥製がいっそう不吉な印象を与えていた。二人の前のテーブルにはブラッドショー鉄道案内が置かれていた。
「カリスベリから馬車で来るはずがないわ」ミセス・パーキンが言った。「ウイリス博士は前任者のような厩舎をお持ちじゃないもの。ミセス・フリントがカリスベリで毎年恒例の共励会に出たとき、ウイリス博士は、主教たるもの、教会の仕事に絶対必要と認められるもの以外、乗り物に贅を凝らしてはいけないというお考えだって聞いたそうよ。彼女自身、主教の馬車とすれ違ったんだけど、御者は服装もみすぼらしくて、馬は二頭ともどうしようもない駄馬だったんですって」
「同じことをわたしも聞いたよ」と主任司祭は相槌を打った。「馬車に自分の紋章を描かせないということだね。何もせずそのままで充分ということらしい。カリスベリからここまで馬で来ることはあり得ないな。たっぷり二十マイルあるから」
「馬車じゃないとすれば、十二時十五分の汽車で来るしかないわ。それだと礼拝まで二時間十五分の余裕がある。カランで用事だなんていったい何かしら。どこでお昼を召し上がるのかしら。二時間十五分も何をなさるっていうのかしら」
ここにもう一つの謎があらわれたわけだが、これに答えられるのはカランにただ一人しかいなかっただろう。それはミスタ・シャーノールである。ちょうどその日、一通の手紙がオルガン奏者のもとに届いた。
カリスベリ、主教公邸
親愛なるシャーノール
(もう少しで「親愛なるニック」と書きそうだったよ。あれから四十年がたち、わたしのペンも少しこわばってしまったが、この次は「親愛なるニック」と書けるよう、きっと正式な許可をくれたまえよ)わたしの筆跡は忘れたかもしれないが、わたしのことは忘れていないだろう。新しい主教となったのが、このわたし、ウイリスだということを知っているかい。きみがわたしのすぐそばにいることを知ったのはほんの二週間前のことだ。
何と喜ばしきことだろう
輝ける友情を再び蘇らせることは――
さっそくなんだが、わたしはきみに昼飯をたかろうと思っている。わたしは堅信礼のために今日から二週間後、十二時四十五分にカランに行き、二時三十分に司祭館に着かねばならない。しかしそのあいだ、わが友ニコラス・シャーノールよ、わたしに食べ物と避難所を与えてくれないか。言い訳は無用。そんなもの認めないからね。ただ確実に義務を遂行する旨知らせてくれたらいい。
いつも変わらぬきみの友
ジョン・カラム
この手紙を読んだとき、ミスタ・シャーノールの耄碌した身体の中で何かが不思議とざわめいた――いろいろな思いが入り乱れた。大人の心の中に隠れた子供の心が声をあげ、希望に満ちた若い自分が絶望的な年寄りの自分に語りかけた。肘掛椅子に座り目を閉じると、大学の小さな礼拝堂の、オルガンの置かれた二階の張り出しがよみがえってきた。長い長い練習、そして彼が演奏をつづけるあいだ、ずっと満足そうにそばに立って聞き入っていたウイリス。ウイリスは、脇で音栓をひっぱったくらいで音楽ができると思いこみ、嬉しそうにしていた。ウイリスは音楽などちっとも分かっていなかった。しかし趣味がよくて、フーガが大好きだった。
田舎を歩き回って聖堂めぐりをしたこと、そして「ゴシック建築入門」を手に、初期イギリス様式の刳形とイギリスゴシック建築様式の刳形の違いを説明しようとするウイリスの姿が思い浮かんできた。日が落ちて何時間経っても、北の空が澄み切った黄色に染まったままの、かぎりなく長い夏の夕べ。しっとり露にぬれた広い乗馬道が脇を走る、埃っぽい白い道。暗くて神秘的なストウウッドの森。ベックリイの小道に生えたハシドイの香り。チャーウエルの谷に立ち籠める白い霞。それから寮に帰って食べた夕食――記憶は強力な錬金術師で、夕映えだけでなく夕食までも変質させてしまう。なんという夕食だったろう!ルリチシャの浮かぶ林檎酒、ミントソースをかけた冷めた子羊の肉、ミズガラシ、三角形のスティルトンチーズ。そういや、スティルトンチーズは四十年も食べていないぞ!
そう、ウイリスは音楽の知識がなかったが、フーガは大好きだった。ああ、フーガとなるとウイリスは聞き入っていたな!そのときひとつの声がミスタ・シャーノールの記憶によみがえった。「わたしのときは頼むからフーガはやめてくれ」「
主教選出のニュースをはじめて聞いたとき、それが昔の友人であることはもちろん分かった。そのウイリスが会いに来てくれるとは嬉しいじゃないか。ウイリスはあの騒動のことをみんな知っている。わたしがオクスフォードを退学しなければならなくなった事情も。うん、しかし主教は心の広い寛大な男だから、いまさらあんなことをとやかく言わないだろう。ウイリスはわたしが貧しい、尾羽打ち枯らした老人に過ぎないことをよく知っているはずだ。それでもわたしのところに昼飯を食べに来るといっている。しかしウイリスはわたしが今も――。彼は考えつづけるのをやめ、鏡を見てネクタイを直し、外套の第一ボタンを留めると、震える手で左右の頭髪を後ろに撫で付けた。いや、ウイリスはそこまでは知らないし、知られてはならない。悔い改めるに遅すぎることはないのだ。
彼は戸棚のほうにむかい、酒瓶とタンブラーを取り出した。アルコールはほんの少ししか残っていなかったが、彼はそれをタンブラーに残らず注いだ。束の間彼は躊躇した。気弱になった意志が負けるなとみずからを励ました一瞬だった。どうやら彼はこの高価な酒を一滴たりとも無駄にするまいとしているらしかった。彼は酒瓶を慎重にひっくり返し、最後の小さな一滴が瓶を離れ、タンブラーに落ちるのを見た。いいや、わたしの意志の力はまだ完全に麻痺してはいないぞ――まだな。そして彼はタンブラーの中身を火にぶちまけた。淡い青色の炎がぼっと大きく燃え立ち、小さな爆風が窓ガラスを鳴らした。しかし英雄的行為はなされた。彼は心の中で幾つものトランペットが鳴り、「自己に打ち勝った者」(註 ケンピスの「キリストにならいて」から)と叫ぶ賞賛の声を聞いた。ウイリスに知られてはならない、わたしが今も――なぜならわたしは金輪際酒とは縁を切るつもりなのだから。
彼は呼び鈴を鳴らした。ミス・ユーフィミアがそれに応じて出てみると、彼はほとんど跳ね回るように元気よく部屋の中を行ったり来たりしていた。彼女が入ってくると、彼は立ち止まり、踵を合わせて深々とお辞儀をした。
「これはうるわしき城主様。どうぞ従者に跳ね橋を下ろし、鬼戸を上げよとお命じくだされ。肉詰めのパイ、塩漬けの魚、葡萄酒の大樽をご注文なさり、大広間はわがカリスベリ主教をお迎えするにふさわしく飾り立ててくだされ。主教はこのお城で中食をお召し上がりになり、馬に馬草を与えるおつもりですぞ」
ミス・ジョウリフは目を丸くした。テーブルの上に酒瓶とタンブラーがあり、ウイスキーの臭いが芬々と漂っていた。彼女の考えていることが分かると、ミスタ・シャーノールの顔からはしゃいだ表情が消えた。
「いや、違うよ」と彼は言った。「今回は違うんだ。わたしはまったくしらふだよ。ただ興奮しているのさ。主教が昼食を食べにここに来るんだ。あなたはブランダマー
「まあ、ミスター・シャーノール。分かりやすくお話してくださいな。わたしは年をとってぼけちゃっているから、あなたが冗談を言っているのか、真面目なのか区別がつかないのですよ」
そこで彼は心の高揚を抑え、彼女に事実を語った。
「でも、旦那様、いったい昼食に何を差し上げるおつもりですの」とミス・ジョウリフは言った。彼女は常に敬意を示す「旦那様」を適当な回数だけさしはさむように気をつけていた。自分の家柄を誇りにし、生まれに関するかぎり、カランのどんな上流婦人にも引けをとらない自信があったが、訳あって下宿の女主人となった今は、その地位をまっとうするのがキリスト教徒の勤めと思っていた。「いったい昼食に何を差し上げるおつもりですの。聖職者の方にお食事を用意するのは、いつも面倒でほとほと困ってしまいます。美味しいものをあんまりたくさんお出しすると、あの方たちの神聖な天職を充分わきまえていないみたいに思われますでしょう。まるでマルタみたいじゃありませんか、聖職者とのお付き合いからありったけの精神的利益を引き出そうとして、やたら食べ物を差し出そうとあくせくしたり、心配したり、頭を悩ましたりするなんて(註 ルカ伝より)。でも、もちろん、どんな精神的なお方だって肉体を養わないわけには行きませんわ。さもなければ善を施すこともできなくなってしまいますから。ただ、お食事の用意を控えめにすると、ときどき聖職者の方が全部召し上がってしまい、もう食べ物がないと分かると、お気の毒にがっかりなさるのです。そうそう、ミセス・シャープが教区民を招いて、教会伝道集会のあと『代表者』と顔合わせなさったときがそうだった。揚げ物料理が『代表者』の到着前になくなってしまいましたの。おかわいそうでしたわ、長い演説をなさった後で、とても疲れていらしたので、食べ物がないと分かるととてもイライラなさって。もちろんそれはほんの一瞬のことです。でもわたしはあの方が、名前は忘れたけど誰かにこう言うのを聞いたんです。これなら駅の軽食堂でハム・サンドイッチを頼んでおいたほうがずっとよかったって。
食べ物も厄介ですけど、飲み物はもっと厄介ですわ。聖職者の中にはワインを毛嫌いなさる方もいるし、かと思うとお話の前にぜひ一杯という方もいらっしゃいます。つい昨年のことですけど、ミセス・ブルティールが応接間集会を開いて、会合の前にシャンペンとビスケットをお出ししたの。そうしたらスティミイ博士は、酒飲み全員が自堕落だとは思わんが、しかしアルコールは獣の刻印であると考える、そして人々が応接間集会に来るのは、話を聞く前に酔っ払ってうつらうつらするためではないとはっきりおっしゃったの。それが主教ともなればもっと面倒なことになるわ。そういうわけですからねえ、いったいわたしたち何をお出ししたらいいのでしょう」
「そううろたえることはないよ」立てつづけに発せられたことばのあいだにようやく隙間を見つけてオルガン奏者は口をはさんだ。「主教が何を召し上がるのか、わたしは調べたんだ。ある小冊子に何もかも書いてある。ミント・ソース付きの冷めた子羊の肉――子羊のあばら肉だよ――ゆでじゃがいも、それからスティルトン・チーズだ」
「スティルトン?」ミス・ジョウリフはかなり動揺して尋ねた。「あれはとても高いものじゃないかしら」
おぼれる者が一瞬のうちに人生を振り返るように、彼女の心はとっさにウィドコウムの全盛期に、そのチーズ籠の中にあったチーズをことごとく思い浮かべた。あのころはハムとプラム・プディングが垂木から袋に入れて吊り下げられ、搾乳場にはクリーム、地下室にはビールがあった。ブルー・ビニー、グロスター・チーズのかけら、ダブル・ビザンツ(註 恐らくフェタチーズのことだろう)、ときには底にい草をつけたクリーム・チーズもあった。しかしスティルトンは見たことがない!
「とても高価なチーズだと思いますわ。カランで売っているところはないんじゃないかしら」
「残念だな」ミスタ・シャーノールが言った。「しかし何とか見つけにゃならん。主教のお昼にスティルトンはつきものなんだ。小冊子にそう書いてある。ミスタ・カスタンスに頼んで何とか手に入れてください。後で切り方を伝授しますよ。切り方にも決まりがあるんだ」
彼はくすくすと一人妙な笑い声をあげた。ミント・ソース付きの冷めた子羊の肉、その後にスティルトン・チーズ――彼らはオクスフォード式の昼食をするのだ。再びあの若かった穢れのない頃に戻るのだ。
主教の手紙がミスタ・シャーノールにもたらした刺激はすぐに薄らいだ。彼は気分屋で、その神経質な気質の中では欝状態が躁状態のすぐあとを追いかけていたのである。ウエストレイは友人が次の日から過度の飲酒にふけるようになったことに気づいた。目に見えて取り乱した奇妙なそぶりは、オルガン奏者が神経衰弱よりももっと深刻な何かに冒されているのではないかという恐れを抱かせた。
ある晩、仕事で夜更かししていると、建築家の部屋のドアが開いて、ミスタ・シャーノールが入ってきた。顔は青ざめ、眼は驚いたように見開かれている。ウエストレイは厭な感じがした。
「ちょっとわたしの部屋まで降りてきてくれないか」オルガン奏者は言った。「ピアノの位置を変えたいんだが、一人じゃ動かせないんだ」
「今日はもう遅いですよ」ウエストレイは時計を取り出しながら言った。そのとき聖セパルカ大聖堂の鐘が深みのある、美しい音色を悠然と響かせ、夢見る町と沈黙する塩沢に、真夜中まであとたった十五分しかないことを告げた。「明日の朝やったほうがいいんじゃありませんか」
「今晩はだめかね」オルガン奏者は訊いた。「すぐすむんだが」
ウエストレイはその声に落胆の響きを聞き取った。
「いいでしょう」彼は製図板を脇に押しやった。「この仕事はもう充分やりましたから。ピアノを移動しましょう」
彼らは一階に降りていった。
「ピアノのむきを百八十度変えたいんだ」とオルガン奏者は言った。「背面を部屋の中にむけ、鍵盤側を壁にむけるのさ――鍵盤を壁にうんと近づけて、わたしが座る分だけあけるんだ」
「おかしな置き方ですね」とウエストレイは言った。「音響的にそのほうがいいのですか」
「さあ、どうだろう。しかし一休みしたいときに壁に寄りかかれるからね」
配置変えはすぐに終わり、二人はしばらく暖炉の前の椅子に座っていた。
「ずいぶん景気よく火をたいていますね」ウエストレイが言った。「寝る時間だというのに」実際、石炭は山をなすほど放りこまれ、激しい勢いで燃えていた。
オルガン奏者はその石炭を一突きし、彼ら以外誰もいないことを確かめるようにまわりを見た。
「きみはわたしのことを馬鹿な男だと思っているだろう」と彼は言った。「まさにその通りだよ。きみはわたしが酒を飲んでいたと思っているだろう。まさにその通り。きみはわたしが今酔っぱらっていると思っているだろう。ところが違うんだ。聞きたまえ。わたしは酔っぱらっちゃいない。臆病なだけさ。きみとわたしがこの家まで一緒に歩いた最初の晩のことを覚えているかい。真暗で土砂降りだった。それから旧保税倉庫のそばを通るとき、わたしが怯えていたことを覚えているかい。ああ、あの頃から始まって、今はずっとひどくなっている。あの頃でさえ、いつも何かにつけられているという恐ろしい考えに取り憑かれていた――それもすぐ後ろをつけてくるんだ。そいつが何かは知らんが――とにかく何かがすぐ後ろにいることは知っていた」
彼の態度と外見にウエストレイは危惧を抱いた。オルガン奏者の顔はひどく青ざめ、まぶたが奇妙につりあがって瞳の上の白目がむき出しになり、突然恐ろしい光景に直面して眼を見開いたような様子をしていた。敵に追いかけられるという幻想が狂気の初期に最もよく見られる兆候のひとつであることを思い出し、ウエストレイはオルガン奏者の腕にそっと自分の手を置いた。
「興奮しちゃいけません」と彼は言った。「そんなの、みんなナンセンスですよ。こんな夜遅くに興奮するのはよくないですよ」
ミスタ・シャーノールは手を払いのけた。
「そんな気がするのは外に出たときだけだったのだが、今は家の中にいてもしばしば感じる――この部屋にいるときさえ。以前は何があとをつけてくるのか分からなかった――何かがつけてくるとしか分からなかった。でも今はそれが何か分ったよ。それは男なんだ――ハンマーを持った男なんだ。笑っちゃいかん。本当は笑いたくないんだろう。笑えばわたしの気が静まると思っているだけで。しかしその手は食わんぞ。そいつはハンマーを持った男だと思う。顔はまだ見たことがない。しかしそのうち拝ませてもらうことになるだろう。わたしに分っているのは、それが邪悪な顔だということだけだ――悪魔の絵とか、あの手のおどろおどろしい顔じゃない。もっと不吉な顔だ――一見まともに見えるが実は仮面をかぶっているぞっとするような変装した顔だよ。やつは絶えずわたしのあとをつけてくる。わたしはそのハンマーがわたしの脳天を打ち砕くんじゃないかと、いつもそんな気がしているんだ」
「そんなはずあるものですか」ウエストレイはいわゆるなだめすかすような口調で言った。「話題を変えましょう。さもなきゃもう寝ましょうよ。ピアノの位置はこんなものでいいんですか」
オルガン奏者はにやりとした。
「どうしてこんなふうに位置を変えたのか、本当の理由が分かるかい」と彼は言った。「それはわたしが臆病者だからだよ。壁を背にすれば、後ろにまわられることはないからね。夜更けに怖いのを必死に我慢してかろうじてここに座っているということが何回あったことか。そんなにびくびくするくらいなら、さっさと寝ればいいんだが、ただわたしはこんなふうに自分に言い聞かせるんだ。『ニック』――子供の頃は家でそう呼ばれていたんだ――『ニック、尻尾を巻いて逃げるわけにはいかないぞ。まさか幽霊におびえて部屋を出て行ったりはしまいな』それからわたしは頑張って演奏をつづけるんだが、上の空でやっていることもしょっちゅうなのさ。こうなっちゃあ、人間も哀れなものだね」ウエストレイは返すことばがなかった。
「聖堂にいるときも」とミスタ・シャーノールはつづけた。「夜中に一人で練習するのはあまり気が進まない。カットロウが送風器で風を送ってくれていたときは大丈夫だったんだ。あいつは頓珍漢だが、それでも話し相手になる。しかしウオーター・エンジンがつけられてからは、あそこにいると心細くてね、以前ほど行く気がしなくなったのだ。何となくブランダマー卿にもらしたんだ、ウオーター・エンジンのおかげでびくびくせにゃならなくなったと。そうしたらときどき二階の張り出しに行ってお付き合いしましょうと言ってくれたよ」
「それなら今度練習したいときは、早速わたしに知らせてください」とウエストレイは言った。「わたしも行って張り出しに座っていますよ。身体に気をつけてくださいね。なあに、そんな気の迷いなんかすぐにどこかへ消し飛んで、わたしみたいに笑い飛ばすようになりますよ」そう言って彼は微笑むふりをした。しかし夜更けということもあり、彼自身も緊張し神経質になっていた。しかもミスタ・シャーノールの精神状態がこれほどまでに不安定に陥っているという事実は彼を憂鬱にさせた。
主教が堅信礼の日にミスタ・シャーノールと昼食をするという噂はすぐにカランに広まった。ミス・ジョウリフは従兄弟で豚肉屋のミスタ・ジョウリフに話をし、ミスタ・ジョウリフは教区委員として参事会員パーキンに話をした。たった数週間のうちに二度も重要なニュースが人伝に主任司祭に伝わってきたのだ。しかし今回はブランダマー卿がウエストレイを通じて修復工事に大金を差し出したときのような悔しさはほとんど感じなかった。彼はミスタ・シャーノールに憤りを感じなかったのである。この一件はあまりに厳粛重要であって、個人的なつまらない感情の割りこむ余地はなかったのだ。いかなる主教の、いかなる行いもすべからく神の行いであり、この神の定めに憤慨するのは船の難破や地震に腹を立てるのと同じくらい場違いなことだったろう。カリスベリ主教をもてなす役に選ばれ、主任司祭の目にはミスタ・シャーノールがただならぬ人物に見えてきた。これは単に知性があるとか、技術が優れているとか、骨の折れる単調な仕事にまじめに取り組んできたとか、そうしたことだけでは決して得られない評価であった。オルガン奏者は事実上、端倪すべからざる人物となったのである。
司祭館は憶測を巡らしては議論し、議論しては憶測を巡らせた。主教がミスタ・シャーノールと昼食を共にするなど、いったいどうすればそんなことになるのか、どうしてそんなことが起きうるのか、どうしてそんなことをしようという気になるのか、どうしてそうでなければならないのか。主教はミスタ・シャーノールが小料理屋でも開いていると思ったのか。それとも主教はミスタ・シャーノールしか作り方を知らない特殊なものを食べるのか。主教はミスタ・シャーノールを専用礼拝堂のオルガン弾きとして迎えようとしているのか。たしか主教座聖堂に空きはなかったはずだ。憶測は謎というめくら壁に総攻撃をしかけ、痛手を受けて退却した。何時間もそのことばかりを話し合ったあげく、ミセス・パーキンは、もうどうでもいいと投げ出した。
「どういう事情なのか、わたしなんかに分るわけないんですけどね」彼女は例の確信のこもった、断罪するような口吻で言った。つまり、口にこそ出さないが、自分には分かっている、この謎は解決したとしても、どうせ二人の当事者の間にうさんくさい関係があることを明らかにするだけだろう、というようなことを暗示する口吻である。
「どうなんだろうねえ、おまえ」と主任司祭は妻に言った。「ミスタ・シャーノールは主教をしかるべく歓迎できるのかな」
「しかるべく、ですって!」ミセス・パーキンが言った。「しかるべく!今回の一件は最初から最後までしかるべき手順を踏んでいないと思いますわ。あなたがおっしゃっるのは、ミスタ・シャーノールにしかるべき食事を買う金があるかってことかしら。もちろんないに決まっているわ。それともしかるべき皿やフォークやスプーン、しかるべき食事部屋があるかってこと?あるわけないじゃない。それとも彼にしかるべく料理が作れるかってこと?誰が料理をするのよ。あの役立たずのミス・ジョウリフと生意気な姪しかいないじゃない」
参事会員は妻のことばが喚起する快適とは言えない光景に大いに当惑した。
「主教のためにできるだけ便宜をお図りするべきだよ。お困りにならないよう、あらゆる手をつくすべきだと思う。どうかね、多少の不都合は我慢してシャーノールに主教を連れてきてもらい、彼も昼食会に加えるっていうのは。彼だって主教を下宿屋でもてなすなど、前代未聞だってことくらい重々承知しているだろう。ヌートの代わりに彼を六人目に据えればいい。ヌートにお役ご免を言い渡すのは簡単だし」
「シャーノールはろくでもない評判の男よ」とミセス・パーキンが答えた。「きっと酔っぱらって来るわ。そうでなくたって『育ち』も教育もないんですからね。上品な会話についてこられないわよ」
「おまえ、主教はもうミスタ・シャーノールとお昼の約束をなさっているんだから、二人を引き合わせてもとやかく言われることはないんだよ。それにシャーノールはちょっとした学問を身につけている――どこで身につけたのか想像もできんが。だがね、一度やつが短いラテン語をすらすら理解するのを見たことがある。ブランダマー家の座右銘『ファインズにあらざれば死』(本章末尾の註参照)というやつだ。他の人から聞いたのかもしれないが、しかしラテン語が分かるような様子だった。もちろんラテン語の本当の知識は『大学』教育を受けなければ得られないが」――主任司祭はネクタイとカラーを直した――「しかし薬屋とかあの手の連中は門前の小僧で生かじりの知識を持っているからね」
「それにしたって、昼食のあいだじゅうラテン語を話すことはないでしょう」妻が遮った。「あの人を呼ぶ呼ばないはあなたのご自由にどうぞ」
ぞんざいな言い方ではあったが、とにかく許可を得たことに主任司祭は満足し、そのあとしばらくしてシャーノールの部屋を訪ねた。
「堅礼式の日なんだが、是非ともうちへ昼食にきてほしいと、ミセス・パーキンが切望している。妻は主教の同意を待って、きみに招待状を送るつもりだったんだ。しかし聞くところによると」彼は怪訝そうに、ためらいながら言った――「聞くところによると、主教はきみとお昼を食べるかもしれないんだってね」
参事会員パーキンの口の端がぴくりと動いた。主教が安下宿でミスタ・シャーノールとお昼を共にするというのは、滑稽きわまりない図で、彼は吹き出しそうになるのを必死にこらえていた。
ミスタ・シャーノールはその通りと頷いた。
「ミセス・パーキンはね、主教をおもてなしするのに必要なものが、きみの宿にあるかどうか心配していたよ」
「その点はお任せください」とミスタ・シャーノールが言った。「今は少々みすぼらしく見えますがね。椅子という椅子をみんな椅子張り職人に出しているので。金箔の剥げを直してもらっているんですよ。もちろんカーテンも新調するし、ここの女主人は一番いい銀器を磨きはじめています」
「これはミセス・パーキンの思いつきなんだが」と主任司祭はつづけた。彼は言うべきことを言おうとするあまり、オルガン奏者のことばにはほとんど注意を払わなかった――「ミセス・パーキンの思いつきなんだが、お昼は主教を司祭館にお連れしたほうがよくはないかね。準備の手間が省けるし、もちろんきみも一緒にお昼を食べたらいい。われわれのほうに不都合なことはないんだ。ミセス・パーキンはきみがお昼に加わってくれたら喜ぶだろう」
ミスタ・シャーノールは頷いたが、今度は不賛成の頷きだった。
「ご親切にありがとうございます。ミセス・パーキンのお心遣いにも心から感謝します。しかし主教はこの家でお昼をいただくとおっしゃってますからな。主教のお望みに異を唱えるわけにはいきません」
「主教はきみの友達なのかい」と主任司祭が訊いた。
「友達とはいえません。四十年会っていないんですから」
主任司祭には何が何やらさっぱり分らなかった。
「ひょっとして主教は勘違いしているのかもしれないね。この下宿が今でも宿屋だと――つまり神の手だと思っているのかもしれないね」
「かもしれませんな」とオルガン奏者は言った。短い間があった。
「考え直してくれるとありがたいね。わたしがミセス・パーキンにこう伝えちゃまずいかな、主教にはきみから司祭館でお昼を食べるように要請すると――いや、もちろん、きみも一緒に」――彼はいやいや最後のことばを発した。主教を主教とは釣り合いのとれない男と一緒にしたり、限られた歓待のドアをミスタ・シャーノールに開くのは胸のうずく思いであったが――「きみも一緒にお昼を食べ来ると伝えては」
「残念ですが」とオルガン奏者は言った。「残念ですがやめておきましょう。特別な礼拝ですから準備が大変なんです。司祭が聖堂に入場するとき『見よ、英雄は還りぬ』を演奏するなら、練習時間も必要です。ご存じでしょうが、ああいう曲は多少指を慣らしておかなければなりませんので」
「最高の演奏を期待しているよ」攻略は不首尾に終り主任司祭は兵を引き上げた。
ミスタ・シャーノールの妄想、とりわけ誰かが後をつけてくるという妄想は、ウエストレイに好ましからざる印象を与えた。彼は同宿人の身を案じ、そのような状態にある人間はみずからに危害を与えることもあると、思いやりのある目で彼を監視しようとした。夕方になるとたいていミスタ・シャーノールの部屋に降りてゆき、あるいはオルガン奏者を上の自分の部屋に招いた。高齢者の一人暮らしにつきまとう孤独が妄想を生み出す大きな原因に違いないと考えたのである。ミスタ・シャーノールは夜になると、かつてマーチン・ジョウリフの持ち物だった書類の整理と閲読に没頭した。書類は生涯をかけて集めただけに膨大だった。中身はメモの切れ端とか登記簿からの書き抜きとか系図がびっしり書きこまれた写本とか、それに類したものだった。最初、これらを分類あるいは破棄する目的で調べはじめたとき、彼はこの仕事に乗り気でないことをありありと示していた。理由さえあれば喜んで仕事を中断したり、ウエストレイの援助を請うた。一方建築家はもともと考古学や系譜学を好み、かりにミスタ・シャーノールが彼に書類全部の閲読を任せたとしても不快には思わなかっただろう。彼は一人の男の全人生を無駄にさせたキメラの由って来たるところを突き止めたかった――マーチンがそもそもブランダマー家の爵位継承権を持つと信ずるに至った、その原因を探り出したかった。はっきり意識はしていなかったが、アナスタシア・ジョウリフに惹かれはじめていたことがさらなる動機となっていたのかもしれない。この調査によって彼女の運命が左右される可能性もあったからである。
ところが書類に対するオルガン奏者の態度がほどなく変化したことにウエストレイは気がついた。ミスタ・シャーノールはこれ以上建築家が書類を調査することを厭がった。そしてみずからその研究に多大の時間と注意をむけるようになり、用心深く鍵をかけてそれらを保管した。ウエストレイは性格的に人に疑われるような真似を嫌った。彼は早速その問題に首をつっこむのをやめ、ミスタ・シャーノールに対して、書類にはもはや何の関心もないようなふりをした。
アナスタシアはあんな妄想に根拠があるわけがないと大笑いした。彼女はミスタ・シャーノールを笑い、ウエストレイを冷やかし、お二人とも雲形紋章を探して旅に出ることになるわ、と言った。しかしミス・ユーフィミアにとっては笑い事でなかった。
「ねえ、あなた」と彼女は姪に言った。「富や財産を求める旅というのは、どんなものであれ神様の御心にかなったものじゃないのよ。ものを探し当てようなんてすることは」――彼女は女性らしく「もの」ということばに重々しい包括的意味をこめた――「たいてい人間によくない影響を与えるの。私たちにとって貴族であり金持ちであることがよいことなら、神様はきっとわたしたちをそういう境遇につけてくださるわ。でも自分が貴族であることを証明するなんて、白昼夢にふけったり易を見てもらうようなものよ。偶像崇拝は罪深い魔術みたいなものね。そこに神様の祝福はないわ。わたし、マーチンの書類をミスタ・シャーノールに渡したことを、これからずっと後悔する。自分で調べるなんてとても耐えられそうになかったし、もしかしたら小切手みたいな貴重なものが混じっているかもしれないと思って渡したんだけど。さっさと燃やしてしまえばよかった。ミスタ・シャーノールは全部読み終わるまで捨てるつもりはないと言っている。あんなもの、マーチンにとって祝福でも何でもなかった。あのお二人も魔力に惑わされなければいいけど」
(註 「ファインズにあらざれば死」の原文は Aut Fynes, aut finis。finis には「境界、領土、限界、目標、終わり、末端、最後」などの複数の意味がある。また、この座右銘がつくられた当時の発音から考えると、Fynes は finis の複数形 fines ととることも可能である)
第十二章
修復計画がブランダマー卿の寛大な寄付によってしかるべく修正され、作業も順調に進捗する段階に入ると、当初は細かい点までみずから厳しい監督の目を光らせていたウエストレイにも、ときには軽くくつろぐ余裕が生まれた。ミスタ・シャーノールは夕べの祈りのあと、半時間以上も演奏していることがしばしばあり、そんなときウエストレイは暇をとらえてオルガンのある張り出しにむかった。オルガン奏者も彼を喜んで迎え入れた。どれほどさりげない形ではあれ、そうした訪問に示される関心のしるしをありがたく思ったのだ。ウエストレイは専門知識はなかったものの、張り出しの見慣れぬ様子に大いに興味をそそられた。そこはそれ自体でひとつの不思議な王国をなしていた。カラン大聖堂の聖歌隊席を身廊からへだてる、巨大な石の障壁の上にあり、まるで無人島ででもあるかのように、外界から遠く切り離されているのである。そこへ行くには障壁の南端、身廊の側から狭い石の螺旋階段を登らなければならなかった。この窓のない階段は、下のドアが閉められると、登っている者が一瞬うろたえるほどの真暗闇に包まれる。彼は足で階段をさぐり、中心の小柱に手をかけながら進まなければならなかった。それは過去、数え切れないほどの手によって大理石のような滑らかさにまで磨きあげられていた。
しかし六段も登ると暗闇は薄れていく。まず夜明け前の薄明かりが見え、やがて階段の上に達し、張り出しに足を踏み入れると柔らかな光があふれてくる。そこで何よりも目を惹くものが二つあった――一つは南袖廊の入り口に架かる、巨大なノルマン様式のアーチで、その表面には雅やかで繊細な刳り形が施されていた。もう一つはその背後にあるブランダマー・ウィンドウの上端で、複雑きわまりない狭間飾りの中心に、海緑色と銀色の雲形紋章が光り輝いている。それから彼は延々とつづく身廊の天井を見上げたり、ノルマン様式の穹窿天井を山形模様のリブが交差し、斜め十字を形作りながら柱間を区切っている様子を眺めたり、中央塔のランタンに目をやり、ヴィニコウム修道院長の垂直様式の羽目板が軽やかな線を描いて上昇し、はるか頭上の窓のところで消えているのを眼で追ったりするのである。
張り出しにはありあまるほどの空間があった。ゆったりした線に囲われ、演奏者の席の横には椅子を一、二脚置く余裕があった。側面には楽譜を納めた背の低い本棚が並んでいる。この棚にあったのはボイの偉大な二つ折り版、クロフト、アーノルド、ペイジ、グリーン、バティシル、クロッチ――どれもこれも裕福だったその昔、「カラン大聖堂主任司祭兼創設委員」が惜しみなく金を出して購入した本である。しかしこれらは後の世に生まれた子供たちにすぎない。そのまわりには年上の兄弟たちが控えていた。カラン大聖堂には今も十七世紀の楽譜が残されていたのだ。それらは有名な楽譜集で、百冊以上あり、古い黒光りする子牛革の装丁に、大きな金の丸い浮き彫り模様が施され、どの表紙の中央にも「南側聖歌隊席テノール」とか「北側聖歌隊席コントラテノール」とか「バス」とか「ソプラノ」などという字が刻印されていた。中を開くと赤い線で縁取られた羊皮紙があらわれ、実に黒々とした太い活字で礼拝名や「ヴァース・アンセム」、「フル・アンセム」と書かれている。次に目次が何ページもつづく――ミスタ・バテンにミスタ・ギボンズ、ミスタ・マンディにミスタ・トムキンス、ブル博士にジャイルズ博士、すべてがきれいに整理されページ番号を打たれていた。ミスタ・バードは、とうに墓場の土と化した歌い手たちを鼓舞して「太鼓を打て、快いハープを、ビオールを鳴らせ」と歌わせ、六つの声部と赤い大文字を使ってもう一度「快いハープを、ビオールを鳴らせ」と繰り返させた(註 バードのアンセム「神にむかいて喜びもて歌え」から)。
オルガンのある張り出しは埃だらけだった――舞い落ちる埃、舞い上がる埃、虫に喰われた木の埃、ぼろぼろになった革の埃、蛾に喰われてずたずたになったカーテンの埃、古い緑のベーズの埃。しかしミスタ・シャーノールはこの埃を四十年間吸いつづけ、他のどこよりもここにいると気持ちが落ち着くのだった。ここがロビンソン・クルーソーの島だとしたら、彼こそはクルーソー、見渡すものすべての上に立つ支配者だった。
「ほら、この鍵をあげるよ」彼はある日ウエストレイに言った。「階段の入り口の鍵だ。しかし来るときはあらかじめ知らせるか、階段を登るときに音を立ててくれ。びっくりさせられるのは嫌なんだ。入ったらドアを閉めること。鍵はかってにかかる。わたしはいつもドアに鍵をかけるよう注意しているんだ。さもないと、どんなやつがここに上がって来ようとするか分からないから。まったく不意を襲われるのはたまったものじゃない」そう言って彼は目に奇妙な色を浮かべ、後ろをちらりと振り返った。
主教がやってくる数日前、ウエストレイはミスタ・シャーノールとともにオルガンのある張り出しにいた。彼は礼拝が行われているあいだ、ほとんどずっと隅の椅子に座って、明かり層の窓と交差リブが織りなす光と影の不思議なダイヤモンド模様を見ていた。野外にいた者は白い雲の島々が青い空を渡っていくのを目にしただろう。その一つ一つの雲が通り過ぎるとき、刳り形を施された重量感あふれる内部のリブは交差する線をくっきりと際立たせ、ニコラス・ヴィニコウムがリブの交点に飾りとして加えさせた「ブドウの葉の輪に梳き櫛」という判じ絵紋をあざやかに浮上がらせた。
建築家はのしかかる天井に、ほとんどいわれのない畏怖を抱くようになっていた。しかもその日は不思議な効果に見とれて、ミスタ・シャーノールに話しかけられるまで、礼拝が終わったことすら分らなかった。
「きみはわたしの変ニ長調のサーヴィスを聴きたいといっていたね。『シャーノール変ニ長調』を。聴きたいなら、これから弾いてあげよう。もちろん合唱なしだから、だいたいの感じしかつかめないよ。もっともここの聖歌隊の声じゃ、まともに曲を鑑賞できるか怪しいがね」
ミスタ・シャーノールが色あせた手書きの楽譜を見ながらサーヴィスを演奏しはじめると、ウエストレイは夢心地から覚めて注意を集中する姿勢になった。
「ほら」彼は曲の終りに近づいたとき言った。「聴いてごらん。ここがいちばん盛り上がるんだ――フーガ風のグローリアで、ペダル音で終わるんだ。ほら、ここだよ――主音のペダル音だ、この変ニ音、新しい足鍵盤の端っこの突き出たペダル、これを最後まで押さえておくんだ」そう言って彼はペダルに左足を載せた。「マニフィカトをこういうふうに終えるのはどうかね」演奏を終えて彼は言った。ウエストレイはすぐにありきたりの賞賛のことばを浴びせた。「悪くないだろう?しかしこの作品の聴きどころはグローリアだよ――本物のフーガじゃないんだが、フーガ風の曲で、ペダル音を使っている。さっきのペダル音の効果は分ったかい。あの音だけちょっと響かせてみるよ。そうすればはっきり識別できるから。それからもう一度グローリアを弾こう」
彼が変ニ音のペダルを押さえると開管の鳴り響く音が長い身廊のアーケードを抜け、トリフォリウムの奥の暗がりにこもり、のしかかるような穹窿天井の下を通って、わななきながらランタンの中を昇っていった。最後のほうになると、それは瀕死の巨人のうめき声のように聞えた。
「やめてください」とウエストレイは言った。「ずんずん響く音は我慢ならない」
「分かった。じゃあ、グローリアを弾くから聴いていたまえ。いや、もう一回サーヴィス全体を弾いたほうがいいな。そのほうが自然に曲の最後に入っていける」
彼はサーヴィスを再度演奏しはじめた。独創的な音楽家が自作を演奏するとき、こめずにはいられない細やかな注意と感情をこめて。同時に彼は嬉しい驚きを味わってもいた。何年も顧みず、半ば忘れかけていた作品が、想像以上の出来栄えで力強いことに気づいたのである。衣装ダンスから古いドレスを出してみたら、色褪せもせず、いまだに値打ちがあると分かってびっくりするようなものだ。
ウエストレイは張り出しの隅の壇の上に立っていた。そこからだとカーテン越しに聖堂内が見渡せた。音楽を聴きながら彼の眼は建物の中をさまよった。しかしだからといってその分、音楽をおざなりに聴いていたわけではない。いや、それどころか、かえって真剣に耳を傾けていたのである。何人かの文人が気づいているように、文学的感受性と表現能力は音楽の刺激を受けて活気づくのだ。大聖堂はがらんとしていた。ジャナウエイは午後のお茶を飲みに帰っていた。扉には鍵がかけられ、部外者は誰も入って来られない。オルガンのパイプの声を除けば、いかなる音も、いかなるささやきも、いかなる声も聞えなかった。ウエストレイは耳を澄ました。いや、待てよ。他には何の声も聞こえないだろうか。聞こえるものは何もないだろうか――彼の心の中で何かが語ってはいないだろうか。はじめのうち、それは「何か」としか意識されなかった――彼の注意を音楽から逸らそうとする「何か」としか。しかし注意を妨げるこの力は、そのとき、いまひとつの声に変わった。かすかな声だが、「シャーノール変ニ長調」が流れる中でもはっきりと聞こえた。「アーチは決して眠らない」とその静かな不吉な声が言った。「アーチは決して眠らない。彼らはわれわれの上に背負いきれないほどの重荷を載せた。われわれはその重量を分散する。アーチは決して眠らない」。彼は塔の下の交差部のアーチに目をむけた。そこ、南袖廊のアーチの上には巨大なひび割れが黒々と、稲妻のようなねじくれた姿を見せていた。それは過去百年間見せていた姿と少しも変わっていないように思えた。普通の観察者なら何ら異変を認めなかっただろう。しかし建築家は違った。彼は一瞬割れ目を凝視し、ミスタ・シャーノールのことも音楽のことも忘れて、張り出しを降り、石工たちが天井下まで組み上げた木の足場へむかった。
ミスタ・シャーノールは彼が下に降りたことすら知らないまま、陶酔したようにグローリアへと突き進んだ。「フル・グレイトにしてくれ」と後ろにいるはずの建築家に呼びかけた。「第一鍵盤の音栓をリード以外全部入れるんだ」しかし返事がないので彼は自分で音栓を引っ張り出した。「今度のほうがうまくいったよ――ぜんぜんいい」最後の音が鳴り止んだとき、ウエストレイに感想を聞こうとして振り返った。しかし張り出しには誰もいない。彼は一人だった。
「あいつめ!」と彼は言った。「出るなら出ると、少なくとも一言断るべきだ。ふん、確かにつまらん曲だ」彼はその厳しい批評とは反対に別れを惜しむような愛情のこもった手つきで手書きの譜面を閉じた。「駄作だな。どうして聴いてくれる人がいるなどと思ったのだろう」
ウエストレイがベルヴュー・ロッジのオルガン奏者の部屋に飛びこんできたのは二時間も後のことだった。
「申し訳ありませんでした、シャーノール。挨拶もせず立ち去ったりして。音楽の分らない無礼なやつだと思ったでしょうね。でも本当はびっくりしすぎて、思わず理由を言わずに出て行ってしまったのです。演奏の最中にたまたま南袖廊のアーチの上の大きな割れ目を見上げたのですけれど、そうしたらごく最近動いたような跡があったのです。すぐ足場に登って、それからずっとそこにいたのです。まずいですよ。割れ目が大きく広がっているみたいです。深刻な事態になるかも知れないので、今晩、最終列車でロンドンに行くことにしました。すぐサー・ジョージ・ファークワーの意見を聞かなければなりません」
オルガン奏者は唸った。繊細な心が受けた傷は深くうずいたが、憤りはすでに優しく慰められていた。ウエストレイには一言文句を言うつもりだったが、説明を聞くと至極もっともで、彼はその機会が奪われたことを残念に思った。
「謝るなんてよしてくれ。きみが出て行ったとは気づかなかったよ。いたことすらすっかり忘れていた」
ウエストレイは自分の発見に気を取られ、相手の不快感を感じ取ることができなかった。彼は慌てることを機敏と勘違いする興奮しやすい人間の一人だった。
「そういうわけで、半時間後にロンドンへ発ちます。今回ばかりはいい加減に放って置くわけにいきません。アーチに支柱をかうまでオルガンの演奏を中止するとか、聖堂の使用を全面的に禁止するなんてことにもなりかねませんよ。もう荷物をまとめなくては」
こうして英雄のごとき迅速と決断を持って彼は最終列車に飛び乗り、沿線の各駅で停車を繰り返しながら夜の大部分を過ごした。手紙を一本出すか、翌日の朝、カラン街道駅から急行に乗っても同じように目的を達することができたのであるが。